「朝ぼらけ 有明の月と みるまでに 吉野の里に ふれる白雪」
小倉百人一首にも収められているこちらの歌。
作者は平安時代に蝦夷討伐で活躍した武人・坂上田村麻呂の子孫であることをご存知でしょうか。
そこで今回は、坂上是則という人物についてご紹介します。
坂上是則とは?
坂上田村麻呂から数えて5代目。
坂上是則は平安時代中期の役人であり歌人、そして蹴鞠の名人でもありました。
三十六歌仙の一人

冒頭でご紹介した歌ですが、
吉野の里に雪が白く降り積もっている
という意味です。
さらに坂上是則は三十六歌仙(藤原公任が選んだ、36人の優れた歌人。小野小町や紀貫之などがいる。)の一人にも選ばれており、
征夷大将軍の子孫らしくないと言えば、らしくないですよね。
ですが坂上氏の家系図を遡ってみると、阿知使主にたどり着きます。
阿知使主とは古代に日本にやって来た渡来人で、東漢氏という氏族の祖。
東漢氏といえば
・文筆
・財務
・外交
などに優れていたことで有名で、そこから分かれたのが坂上氏なのだそう。
その後坂上氏は、「武」でも存在感を放つようになります。
ですが、もとをたどれば頭の良い氏族だったのですね。
ということで、坂上是則という優れた歌人が出たことにも納得です。
蹴鞠の名人

坂上是則は歌人としてだけでなく、蹴鞠の名人でもありました。
蹴鞠とは鞠を落とさずに何回けり上げられるか、という遊びのことです。
一人ではなく、通常は8人で行います。
蹴鞠は、当時の貴族の間で大流行(のちには武士たちの間にも浸透)。
坂上是則は御所で催された蹴鞠の会で206回連続で鞠を蹴り、醍醐天皇からご褒美をもらったという逸話を持っています。
現在のようなサッカーのリフティングとは違い、貴族の衣装で革製の鞠を蹴ったのですから驚きですよね。
きょうのまとめ
今回は坂上田村麻呂の子孫・坂上是則について、簡単にご紹介しました。
坂上是則とは?
② 三十六歌仙の一人にも選ばれた、優れた歌人でもあった
③ 醍醐天皇から褒美を賜るほどの蹴鞠の名人だった
こちらのサイトでは他にも、坂上田村麻呂にまつわる記事をわかりやすく書いています。
より理解を深めたい方は、ぜひお読みになってくださいね。
坂上田村麻呂の年表を含む【完全版まとめ】記事はこちらをどうぞ。
関連記事 >>>> 「坂上田村麻呂とはどんな人物?簡単に説明【完全版まとめ】」
その他の人物はこちら
奈良時代に活躍した歴史上の人物
関連記事 >>>> 「【奈良時代】に活躍したその他の歴史上の人物はこちらをどうぞ。」
時代別 歴史上の人物
関連記事 >>>> 「【時代別】歴史上の人物はこちらをどうぞ。」

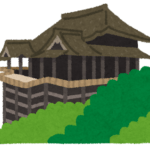

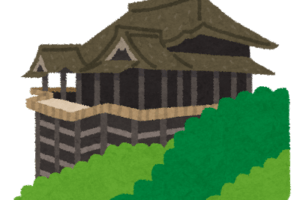
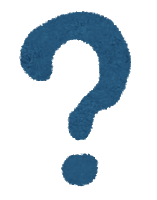







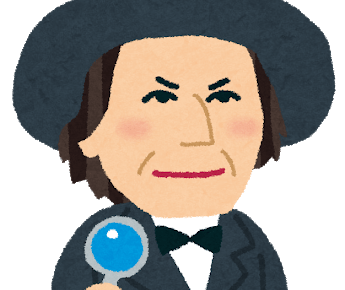

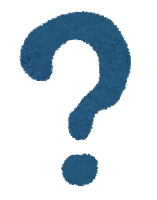
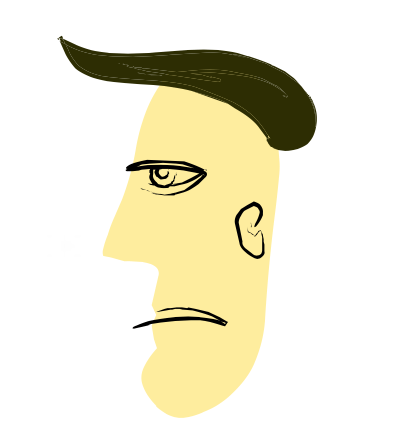
コメントを残す