日本人なら一度は耳にしたことがある「大化の改新」ですが、
どんな出来事で、
中大兄皇子はどのように行ったのでしょうか。
今回は、背景や一連の流れを見つつ大化の改新について説明します。
タップでお好きな項目へ:目次
そもそも、大化の改新とは
「大化の改新」とは、
646年に発布された、天皇中心の集権国家を目指す政治改革のことです。
中大兄皇子と中臣鎌足が蘇我入鹿を殺害した事件と思われがちですが、
実は、その後の一連の政治改革のことを指しています。
蘇我入鹿の殺害事件自体は、
「乙巳の変」といいます。
大化の改新の中心人物、中大兄皇子とは?
中大兄皇子は、第34代舒明天皇の第二皇子であり、
第35代皇極天皇の第一皇子にあたります。
後の第38代天智天皇として有名ですが、大化の改新のきっかけとなる、
「乙巳の変」時は19歳の若者でした。
大化の改新の背景

聖徳太子(574-622)の亡き後、豪族の蘇我氏の権勢が強くなりました。
ついに蘇我氏は聖徳太子の息子である山背大兄王とその一族を滅ぼしてしまいます。
その後、蘇我氏の勢いはますます強くなり、天皇の力を凌ぐほどになりました。
皇子の中大兄皇子と側近の中臣鎌足は危機感と不満を抱き、蘇我氏を倒す為の計画を立てました。
大化の改新のはじまりは「乙巳の変」
645年、当時の宮殿だった飛鳥板蓋宮で
ついに、中大兄皇子と中臣鎌足の蘇我氏打倒計画が実行されました。
これが乙巳の変です。
天皇も出席する儀式の最中に、中大兄皇子が蘇我入鹿を殺害します。
計画では別に斬り込み役がいましたが、恐れをなして躊躇したので中大兄皇子が直接手を下しました。
蘇我入鹿は皇極天皇に、
「私が何をしたというのですか?」
と訴えますが、天皇は無言で殿中に戻ってしまいます。
翌日、入鹿の父親である蘇我蝦夷も自害に追いやられ、蘇我氏は権力を失いました。
その後「乙巳の変」に関係した人間が裁かれることはなく、中大兄皇子は大化の改新を推し進めることになります。
大化の改新の具体的な政策
乙巳の変以前、豪族は非常に力を持っており、
天皇でさえ豪族の支配する土地や民を、彼らの許可なく使うことは出来ませんでした。
中大兄皇子は天皇が直接、土地や民を支配する中央集権国家を目指して大化の改革を始めます。
この中央集権国家は唐(現在の中国)にならい、律令によって治められたので、律令国家と呼ばれます。
律令とは法律や刑罰のことをいいます。
公知公民と班田収授法
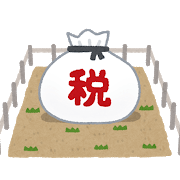
公知公民とは、それまでの土地の私有を禁じ、
全ての土地や人民は国(=天皇)のものであるという国の方針です。
国は豪族から接収した土地を人民に与え、人民が死ぬと土地を返却させました。
この土地に作物の取れ高による税がかけられます。
この仕組みを「班田収授法」といいます。
豪族から貴族へ
土地の接収の代わりに豪族は、食封を与えられることになりました。
また、有力な豪族は国の政治に参加することになりました。
国の政治に参加することを許された豪族達を「貴族」 と呼びます。
役人派遣と税制度
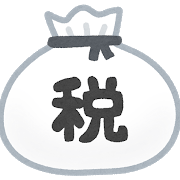
首都が制定され、豪族から取り上げた土地も整備されました。
それまで豪族が支配していた土地は、国から役人が派遣されることになりました。
また戸籍とそれをもとにした、租・調・庸の税制度がつくられました。
租・調・庸とは、
稲の取れ高3%
・調
織物や地方の特産物
・庸
年に10日間都で労働する(もしくは布を収める)
ことを表しています。
年号
日本で初めて年号を定め、「大化」としました。
この「大化」という年号から、この改革を「大化の改新」とよんでいます。
きょうのまとめ
今日は、中大兄皇子が行った大化の改新を紹介しました。
いかがでしたでしょうか。
簡単にまとめると
① 大化の改新とは、蘇我入鹿殺害事件ではなく、その後の政治改革を指す
② 蘇我氏が天皇を凌ぐようになり、危機感をもった中大兄皇子は中臣鎌足と蘇我氏を倒す計画をすすめた
③ 天皇も出席する儀式の最中に、乙巳の変は実行された
④ 天皇を中心とする中央集権国家を目指し、大化の改新が推進された
大化の改新は、初めて日本が国としてまとまるための大切な改革でした。
単なるの権力争いではなく、
「天皇を中心に日本をひとつにする」というビジョンをあってこその、蘇我入鹿殺害だったのですね。
改めて、中大兄皇子の凄さを感じました。
関連記事 >>>> 「中大兄皇子とはどんな人物?簡単に説明【完全版まとめ】」
その他の人物はこちら
飛鳥時代に活躍した歴史上の人物
関連記事 >>>> 「【飛鳥時代】に活躍したその他の歴史上の人物はこちらをどうぞ。」
時代別 歴史上の人物
関連記事 >>>> 「【時代別】歴史上の人物はこちらをどうぞ。」


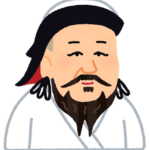



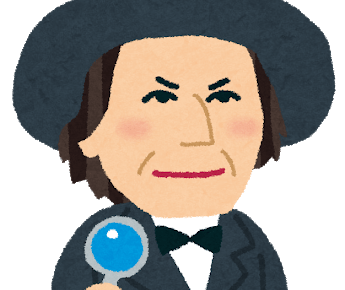


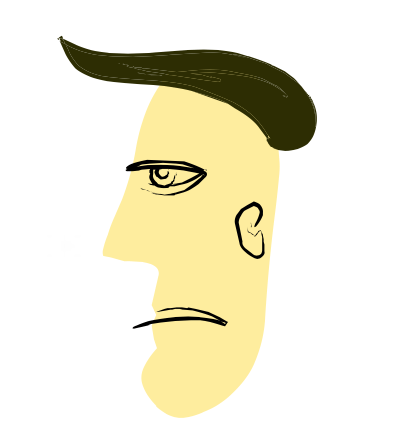
コメントを残す