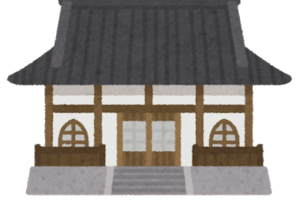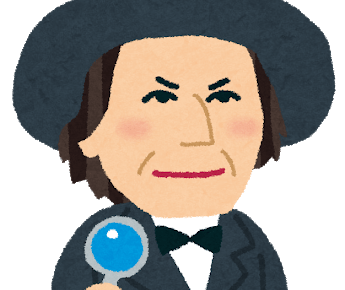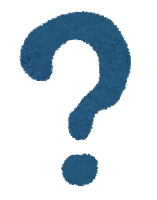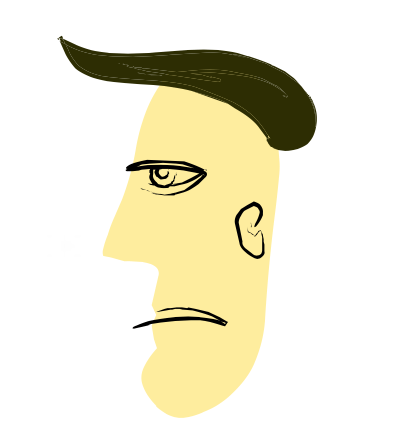『源氏物語』と『枕草子』といえば作品も作者も比較の対象となりがちですね。
これ、もう1000年以上続いてることなんです。
ここでは、そのお約束通りそれぞれの著者、紫式部と清少納言という平安文学の代表二人について比較してみます。
本人たちはもううんざりでしょうけど。
タップでお好きな項目へ:目次
紫式部vs清少納言

紫式部(土佐光起画、石山寺蔵)
出典:Wikipedia
出身と家柄
出身と家柄からみていきましょう。
・藤原為時(学者)の娘
・藤原定方(歌人)が一族
・藤原兼輔(三十六歌仙で堤中納言と呼ばれた)が一族
幼い頃より、女性はたしなまない、とされた漢文を読みこなす才女でした。
・清原元輔(「梨壺の五人」と呼ばれる和歌選者メンバーの一人)の娘
・清原深養父(『古今和歌集』の代表的歌人)は祖父
という文学的に恵まれた家庭に育ち、漢学の素養もあった優秀な女性でした。
年齢
紫式部の誕生年は970年から978年くらいの間、没年が1014年から1031年と幅があり、未詳です。
清少納言の誕生年は966年頃で、1025年ごろに亡くなったと言われていますが、詳細は不明。
清少納言のほうが5、6歳年上のイメージでしょうか。
出仕先と勤務期間
紫式部の出仕先は、藤原道長の娘であり一条天皇の后である中宮彰子。
1006年頃から1012年頃まで彰子の女房兼家庭教師として勤めました。
(それ以前に道長の妻源倫子付きの女房として出仕したとも言われます)
清少納言の主人は一条天皇の最初の后である中宮定子。
993年頃から1000年頃まで出仕していました。
つまり、一条天皇の二人の后である彰子と定子をそれぞれ支える女房が紫式部と清少納言だったわけです。
后の立場の対立は、そのまま女房たちの対立にも繋がりました。
ただ、紫式部と清少納言は出仕した時期がずれており、宮中で顔を合わせることはありませんでした。
ここ、ポイントです。
作品比較
紫式部の作品には、
・『紫式部日記』:宮中の様子を書いた日記
・『紫式部集』:子供時代から晩年に至るまでの自分の歌を選び収めた
があります。
代表作、『源氏物語』は、当時の貴族たちに人気があり、単純に小説として読んでも現代でも楽しめる平安時代の「リアルなフィクション」です。
清少納言の作品としては
・『清少納言集』:小規模な家集
が伝わっています。
『枕草子』は清少納言の感性がきらめく作品であり、同時に決して中宮定子の苦しみや悲劇などのネガティブな実情を描かなかった「操作されたノンフィクション」。
清少納言の固い決意で悲しいほどきっぱりと、明るく描かれた随筆です。
式部も少納言も共に中古三十六歌仙・女房三十六歌仙に選ばれるほどの歌人であり、小倉百人一首に歌が収められています。
性格
紫式部は、藤原道長と父親からのプレッシャーで中宮彰子に出仕したと言われます。
もともと内向的で、宮中でも博学なせいでかえって周囲から敬遠された彼女は、ますます内気に。
漢学の才能をあえて隠そうとさえしたそうです。
しかし、一度筆をとった彼女の『紫式部日記』の人物批評はかなり辛辣です。
ネガティブ思考の人だったかも。
その内向的な性格が、小説を書くときの洞察力を生み、多くの読者をリアリティのある世界へと導きました。
一方の清少納言は、博学で才気煥発。
理解ある主君定子の元で、得意の漢詩の知識を駆使して、殿上人たちとの機知のある応酬が大変上手でした。
彼女の記した『枕草子』には、現代の私たちが読んでも思わず笑ったり、同感したりする箇所が沢山あります。
自慢話を語る部分もありますが、それらも全て定子の価値を高くするための彼女の努力。
明るく一途で、からっとした人物像が感じられます。
ライバル意識していた?

はい、少なくとも紫式部はね。
彼女が中宮彰子に仕えたのは清少納言が朝廷を退いてからはるか後のこと。
実際二人は顔を合わせたことも無かったはずです。
しかし清少納言の噂を聞き、『枕草子』を読んだ紫式部は『紫式部日記』で、少納言の人格と業績を全否定してます・・・。
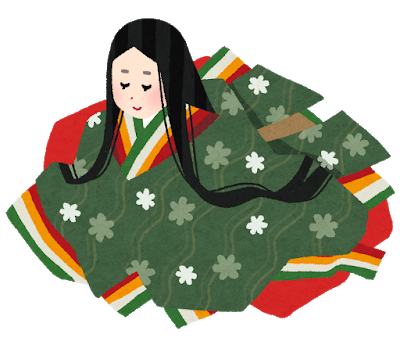
他人より優れたフリをする人は後々見劣りするもの。そういう人間の行く末って大丈夫?
とボロクソです。
清少納言は紫式部の存在を知らなかったので、ノーコメントです。
あはれの『源氏物語』、をかしの『枕草子』は今も
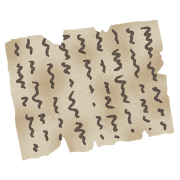
『源氏物語』は「あはれ」、『枕草子』は「をかし」の文学だと言われます。
『源氏物語』という光源氏の恋物語に人々は憧れ、驚き、そして彼の心の推移や取り巻く女性たちの境遇に、読者はいたく共感しました。
「あはれ」とは、人の心理を理解し、人生の真理に感じ入ったときに「ああ」と、心の底からこみ上げてくる心情のこと。
「あはれ」の文学『源氏物語』は、時代によって左右されることのない永遠の情緒を描き、それが世界中の人々に愛されています。
一方、『枕草子』は宮廷生活の事柄が清少納言の光る感性で表現されている随筆です。
美しい風景、可愛らしいしぐさ、いやーな気分になることなど『枕草子』に共感して、
「そうそう、自分もそう思っていた!」
と気付かされる人が沢山いました。
「をかし」とは、そういう新しい発見を喜ぶ気持ちです。
清少納言がひとつひとつ日常から拾い出した、ふとした、輝くようなフレッシュな視点は、1000年経った今でも私たちに「をかし」の気持ちを呼び覚ましてくれます。
きょうのまとめ
紫式部と清少納言。
アプローチも性格も、仕える相手も違う二人でした。
しかし、二人が共に成し遂げたことが一つあります。
それは、平安時代の男たちが富や権力に翻弄されている間に、彼女たち双璧がしっかり平安女房文学の金字塔を打ち立て一世を風靡したこと。
結果、藤原道長に負けないほどの知名度となった優秀な女房たち。
カッコイイと思いませんか。
関連記事 >>>> 「紫式部とはどんな人物?簡単に説明【完全版まとめ】」
清少納言の年表を含む【完全版まとめ】記事はこちらをどうぞ。
関連記事 >>>> 「清少納言とはどんな人物?簡単に説明【完全版まとめ】」
その他の人物はこちら
平安時代に活躍した歴史上の人物
関連記事 >>>> 「【平安時代】に活躍したその他の歴史上の人物はこちらをどうぞ。」
時代別 歴史上の人物
関連記事 >>>> 「【時代別】歴史上の人物はこちらをどうぞ。」