日本の寺院の中でも特別な存在感を放つ、比叡山延暦寺。
平安時代に最澄が開き、戦国時代には織田信長の焼き討ちにあったことでご存じの方も多いでしょう。
歴史の教科書にも、度々登場するお寺ですね。
今回は比叡山延暦寺とはどんなお寺だったのか、今一度振り返ってみましょう。
タップでお好きな項目へ:目次
比叡山延暦寺とは
比叡山延暦寺は、天台宗の総本山。
平安仏教の中心地だったことでも知られています。
東寺を本山とする真言密教を「東密」と呼ぶのに対し、
比叡山を本山とする天台密教は「台密」と呼ばれています。
比叡山延暦寺の場所・広さ
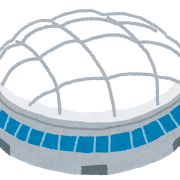
比叡山延暦寺は、滋賀県大津市坂本本町にあります。
といわれますが、滋賀県から京都府にまたがる比叡山全域が境内となっています。
広さはなんと、1700ヘクタールもあるそうです。
といっても、ピンと来ませんよね。
調べてみたところ、東京ドームおよそ363個分だそうです。
ますます、よくわからなくなったような……。
延暦寺とは一つのお寺を指すのではなく、その範囲に存在するお堂の総称のことをいいます。
あまりにも境内が広いので、
- 東塔
- 西塔
- 横川
という、三つのエリアに分けられています。
なお、国宝の根本中堂があるのは、東塔エリアです。
比叡山延暦寺の歴史
次は比叡山延暦寺の歴史について、簡単に振り返ってみましょう。
まずは年表をご覧ください。
- 785年 最澄入山し、草庵を結ぶ。
- 788年 最澄、一乗止観院を創建する【開山】
- 822年 大乗戒壇の勅許
- 823年 延暦の寺号を賜る
- 1571年 織田信長による焼き討ち
- 1584年 豊臣秀吉による根本中堂・戒壇院の再興許可
- 1607年 徳川家康による諸堂再建開始
- 1868年 日吉大社を分離(神仏分離令)
- 1994年 ユネスコ世界文化遺産に登録
開山
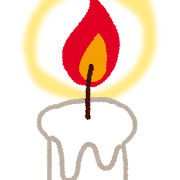
比叡山は延暦寺が建てられる前から、神聖な場所だったようです。
『古事記』には大山咋神(延暦寺の鎮護社である日吉大社の主祭神にもなっています。)が鎮座すると記され、古くから崇められてきたことがわかります。
そんな地に、最澄が入って草庵を結んだのは785年のこと。
3年後には一乗止観院(のちの根本中堂)を創建し、不滅の法燈(本尊の前に掲げられた灯火のこと。現在まで途切れることなく守り続けられています。)を掲げました。
そして最澄の死後、嵯峨天皇より、
- 大乗戒壇(大乗戒を授けるための戒壇。簡単に、お坊さんになるための儀式を行う場所と思って大丈夫です。)の勅許
- 延暦寺の寺号
を賜ります。
山門派・寺門派の対立
その後、比叡山は仏教解釈の違いから山門派と寺門派に分かれ、対立し始めます。
この頃から比叡山は、僧兵(武装した僧侶)を養うようになったといいます。
僧兵はたびたび強訴を行い、朝廷や幕府から恐れられる存在となりました。
信長による焼き討ちと再興

戦国時代に入ると、比叡山は織田信長と領地を巡って対立。
そして信長と敵対していた浅井・朝倉氏と組んだため、焼き討ちにあって全焼しています。
被害は建物だけでなく、三千人もの人々も犠牲に。
さらに、不滅の法燈までもが消えてしまいました。(分灯されていたので無事でした。)
ですがその後、豊臣秀吉・徳川家康らの手によって復興されています。
近現代
明治時代に入ると、それまで延暦寺と一色単に信仰されていた日吉大社が、神仏分離令によって分離されました。
また平成には、「古都京都の文化財」の一つとして世界文化遺産に登録されています。
比叡山延暦寺が輩出した人材
比叡山が輩出した人材は、実に豊富。
一部ではありますが、歴史上有名な人物たちをご紹介しましょう。
円仁・円珍
慈覚大師円仁は、台密を実質的に完成させた人物です。
東北が疫病や大地震に見舞われた際には現地に出向き、死者の追悼を行っています。
また智証大師円珍も、台密の発展に大きな功績を残した人物です。
園城寺(壬申の乱で敗れた大友皇子を弔うために創建された寺院。三井寺とも。)を天台別院として、再興したことでも知られています。
先ほど山門派と寺門派の対立について触れましたが、
円仁の門徒を山門派、円珍の門徒を寺門派といいます。
鎌倉仏教の祖たち
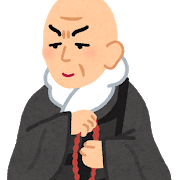
鎌倉仏教を開いた下記の人物たちも、かつて比叡山で修行していました。
- 法然(浄土宗)
- 親鸞(浄土真宗)
- 栄西(臨済宗)
- 道元(曹洞宗)
- 一遍(時宗)
- 日蓮(日蓮宗)
そうそうたるメンバーですね。
彼らは色々な理由で比叡山を去ることになりましたが、
比叡山での修行なくして新仏教は開けなかったのではないでしょうか。
鎌倉仏教は下記で詳しく説明していますので、お読みになってくださいね。
意外!?天台座主だった足利義教
さて、天台座主という存在をご存知でしょうか。
比叡山延暦寺で最高位の僧職のことをいいます。
この地位には、意外な人物が就いていました。
1419年、この座についたのは義円。
のちに還俗し、室町幕府第6代将軍・足利義教となった人物です。
義教はくじ引きで将軍職に選ばれ、恐怖政治を行ったことでも有名です。
その結果、赤松満祐に暗殺されてしまいます。
くじ引きさえ外れていれば、静かに人生を終えられていたかもしれませんね。
また今回は紹介できませんでしたが、他にも良源・源信・良忍・天海らも輩出しています。
きょうのまとめ
今回は最澄の開いた比叡山延暦寺について、簡単に紹介しました。
比叡山延暦寺は、
② 開山から約1200年、様々な対立があったが不滅の法燈は燃え続けている
③ 様々な人材を輩出してきた
こちらのサイトでは他にも、最澄にまつわる記事をわかりやすく書いています。
より理解を深めたい方は、ぜひお読みになってくださいね。
その他の人物はこちら
平安時代に活躍した歴史上の人物
関連記事 >>>> 「【平安時代】に活躍したその他の歴史上の人物はこちらをどうぞ。」
時代別 歴史上の人物
関連記事 >>>> 「【時代別】歴史上の人物はこちらをどうぞ。」




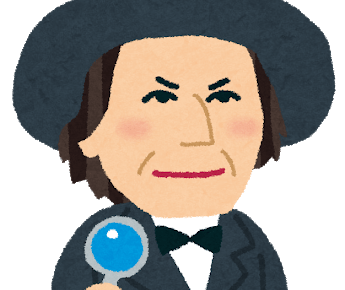


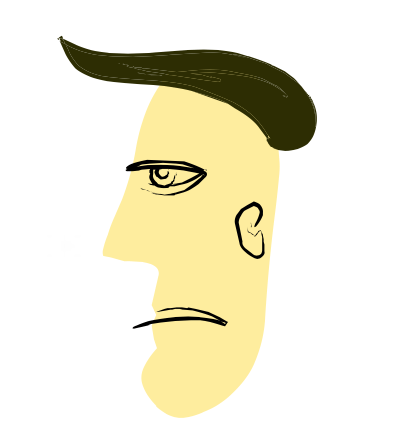
コメントを残す