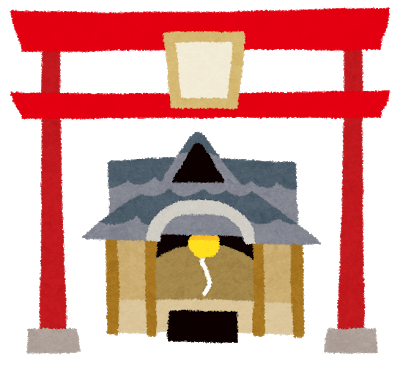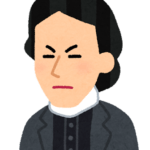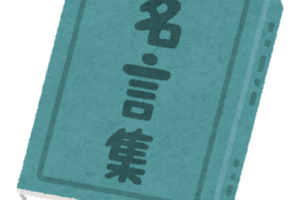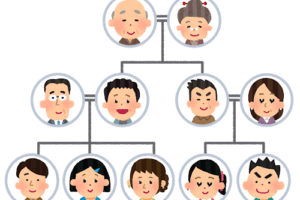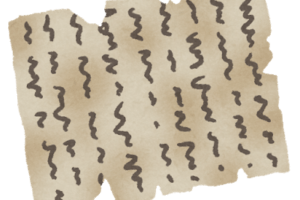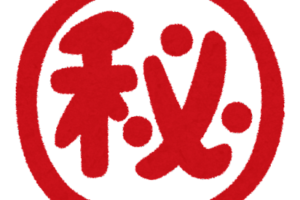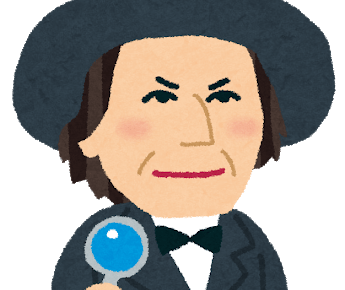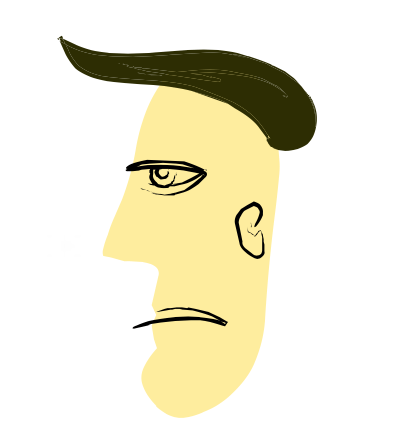会津藩初代藩主・保科正之をご存知ですか?
二代将軍・徳川秀忠の四男として生まれ、
三代将軍・徳川家光とは異母弟に当たります。
家光に重用され、江戸幕府に大きな影響を与えた人物です。
そんな保科正之のお墓、土津神社はパワースポットとして知られているのです。
今回は、保科正之のお墓にスポットを当ててみたいと思います。
タップでお好きな項目へ:目次
保科正之の墓、土津神社とは?
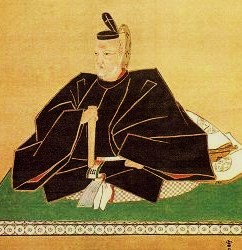
保科正之
出典:Wikipedia
保科正之のお墓についていろいろと調べてみましたので、ご紹介します。
土津神社とは?

土津神社は、福島県耶麻郡猪苗代町にあります。
会津藩祖である保科正之公を主祭神として祭っています。
生前にこの土地を訪れた正之は、猪苗代湖を見渡せるこの場所を気に入り、自分の墓所にするようにと遺言を残しました。
また正之は、
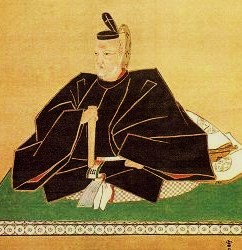
と望んでいたことから、土津神社は磐椅神社の西側に造られたとも言われています。
どちらにしても会津を末永く見守っていきたいと言う正之の思いを感じます。
創建当時は、日光東照宮にも匹敵するような豪華絢爛な建物がありました。
しかし戊辰戦争で、母成峠の戦いに破れた時に猪苗代城代を務めていた高橋権大夫の命により火が放たれ、残念なことに土津神社は全焼してしまいました。
もし建物が残っていたら、国宝級です。
現在は、桜と紅葉の美しい観光スポットとして有名です。
磐梯山の神を祀る磐椅神社とは?
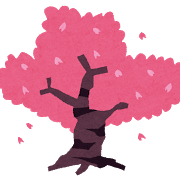
磐椅神社は縁結びのパワースポットとして知られています。
樹齢800年の鳥居杉に宿った山桜が「えんむすび桜」としてメディアで紹介されると、さらに人気に火が付き、良縁を望む女性に人気のスポットとなりました。
磐椅神社の魅力については、旅行系メディアサイト「ヨミドキ!」の下記記事が参考になります。
【福島県猪苗代町】見どころ満載!歴史ある磐椅神社の魅力をたっぷり6つ紹介します
磐椅神社の末社にあたる土津神社は、磐梯山の神様と、会津藩祖・保科正之公のダブルのご利益があるのですから、効果は抜群ですね。
土津神社に参拝した方の感想では
・何かに守られているような気がした
と言ったものがあります。
土津神社には正之公の神聖な気が満ちているのかもしれませんね。
会津藩と共に移封される

前述のとおり、土津神社は福島県耶麻郡猪苗代町に建立されました。
しかし戊辰戦争で会津藩が敗北すると、会津藩は斗南藩、現在の青森県下北半島に移封されます。
それに伴って、土津神社の御神体も斗南藩に移封されます。
明治4年の廃藩置県までの間、土津神社も会津藩士と共に斗南藩にあったのです。
会津藩を見守りたいと願った正之にとっては、置いていかれるよりも一緒に行くことを願っていたのかもしれません。
廃藩置県により御神体は会津に戻り、磐椅神社に納められました。
明治7年に土津神社の再建が始まり、完成すると御神体が戻されました。
きょうのまとめ
保科正之のお墓についていかがでしたか?
会津藩の移封の際も、会津藩と共にあった正之の御霊。
正之は会津の人たちに本当に愛されていたんですね。
正之のお墓と土津神社を守る人たちの集落は、土町と呼ばれ
現在でも民宿街として栄えています。
その他の人物はこちら
江戸時代に活躍した歴史上の人物
関連記事 >>>> 「【江戸時代】に活躍したその他の歴史上の人物はこちらをどうぞ。」
時代別 歴史上の人物
関連記事 >>>> 「【時代別】歴史上の人物はこちらをどうぞ。」