現在、「天皇」と呼ばれる人は何人いるでしょうか?
答えはもちろん一人です。
ですが日本史上、同時に二人の天皇が存在していた時代がありました。
それが「南北朝時代」です。
今回は南北朝時代がどのように始まったのか、わかりやすく紹介していきます。
タップでお好きな項目へ:目次
南北朝時代とは

文観開眼『絹本著色後醍醐天皇御像』(清浄光寺蔵、重要文化財)
出典:Wikipedia
いわゆる南北朝時代とは、1336年から1392年までの57年間を指します。
この間、朝廷が二つ存在するという異例の事態となりました。
一つ(南朝)は現在の奈良県・吉野、もう一つ(北朝)は現在の京都にあったため、
それぞれの位置関係から南北朝時代と呼ばれています。
二つの朝廷は様々な勢力の支持を受け、抗争を始めます。
そして争いは全国に広がり、「南北朝の動乱」と呼ばれる内乱が繰り広げられました。
さらに二つの朝廷は、それぞれが天皇を立てます。
下記を見てもらうとわかりますが、同時期に天皇が二人存在していますよね。
【参考】南北朝時代の天皇
<南朝>
- 後醍醐天皇(1318~1339)(第96代)(※1)
- 後村上天皇(1339~1368)(第97代)
- 長慶天皇(1368~1383?)(第98代)
- 後亀山天皇(1383?~1392)(第99代)
※1 歴代天皇としてカウントされるのは、南朝側の天皇です。
<北朝>
- 光厳天皇(1331~1333)
- 光明天皇(1336~1348)
- 崇光天皇(1348~1351)
- 後光厳天皇(1352~1371)
- 後円融天皇(1371~1382)
もう、めちゃくちゃですね。
ですがこんな状況を生んだのは、後醍醐天皇自身だったのです。
後醍醐天皇が吉野に朝廷をつくるまで
平安時代以降、天皇は京にいるものです。
にもかかわらず、後醍醐天皇は吉野に移って南朝を開きました。
それでは、なぜ後醍醐天皇がこんな行動に出たのか、その理由を順を追って見ていきましょう。
「建武の新政」の失敗

鎌倉幕府に不満を持っていた後醍醐天皇は、倒幕を企てます。
その詳しい理由については、下記の記事をお読みください。
後醍醐天皇の願いは、足利尊氏・新田義貞・楠木正成といった武士たちの活躍によって成し遂げられます。
そして後醍醐天皇は自ら政治を行おうと、「建武の新政」を始めました(1333年)。
ですが「建武の新政」のやり方は武士たちの反感を買っただけでなく、社会までも混乱に陥れてしまいます。
ここら辺の事情をもっと詳しく知りたい方は、下記をお読みください。
足利尊氏との対立
そんな中、足利尊氏が動きます。
中先代の乱(※2)を鎮めるため、建武政権の許可なく鎌倉へと向かったのです。
※2 鎌倉幕府再興のため、北条時行(幕府の権力者であった北条高時の子)が起こした乱のこと(1335年)。
乱を鎮めた後、建武政権は帰ってこいと命令を出しましたが、尊氏はこれを拒否。
建武政権に反旗を翻した尊氏は、後醍醐天皇に忠誠を誓う楠木正成や新田義貞らと、各地で戦いを繰り広げました。
そして足利尊氏はついに京都を占領し、光明天皇(※3)を擁立します(1336年8月)。
※3大覚寺統の後醍醐天皇に対し、光明天皇は持明院統。兄は後醍醐天皇によって廃された光厳天皇。
渡した三種の神器は偽物?

一方後醍醐天皇は比叡山に逃れ、三種の神器(※)も尊氏側に引き渡しています。
※皇位のしるし。八咫鏡・草薙剣・八坂瓊曲玉の三つ。
しかし後醍醐天皇は、渡した三種の神器は偽物であるとして、自身の皇位の正統性を主張。
その年の12月には吉野に逃れ、南朝を開きます。
その後、室町幕府第3代将軍・足利義満の仲介によって三種の神器が北朝側に戻るまで、
南北朝はおよそ半世紀、対立を続けたのでした。
きょうのまとめ
今回は後醍醐天皇が南朝を開いた経緯について、簡単に紹介しました。
② 後醍醐天皇と対立した足利尊氏は、京都で光明天皇を擁立した(北朝)
③ 吉野に逃れた後醍醐天皇は、自らの皇位の正統性を主張した(南朝)
こちらのサイトでは他にも、後醍醐天皇にまつわる記事をわかりやすく書いています。
より理解を深めたい方は、ぜひお読みになってください。
その他の人物はこちら
鎌倉時代に活躍した歴史上の人物
関連記事 >>>> 「【鎌倉時代】に活躍したその他の歴史上の人物はこちらをどうぞ。」
時代別 歴史上の人物
関連記事 >>>> 「【時代別】歴史上の人物はこちらをどうぞ。」



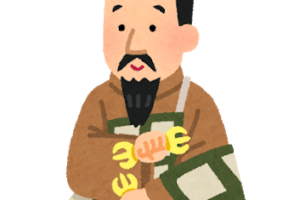

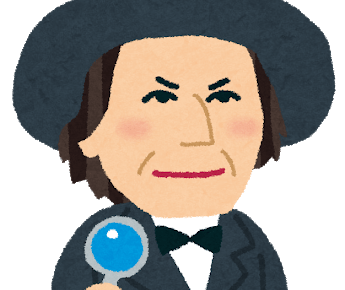


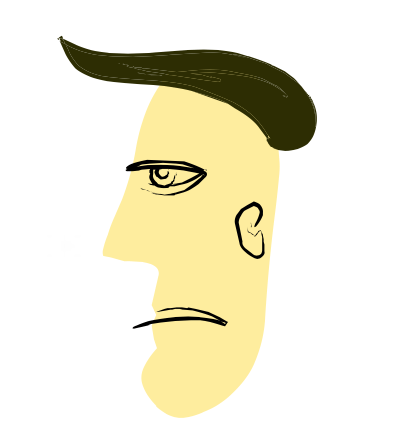
コメントを残す