歴代天皇の中でも、後醍醐天皇は「異形」と言われていることをご存知ですか?
いったい後醍醐天皇とは、どんな人物だったのでしょう。
タップでお好きな項目へ:目次
後醍醐天皇はどんな人?

文観開眼『絹本著色後醍醐天皇御像』(清浄光寺蔵、重要文化財)
出典:Wikipedia
- 出身地:京(現在の京都市)
- 生年月日:1288年11月2日
- 死亡年月日:1339年8月16日(享年52歳)
- 足利尊氏や新田義貞らの協力により、鎌倉幕府を滅亡させた天皇。「建武の新政」崩壊後、吉野に移る。
後醍醐天皇 年表
西暦(年齢)
1288年(1歳)京都に生まれる。(諱、尊治)
1318年(31歳)即位
1321年(34歳)後宇多天皇の院政停止。天皇親政を始める。
1324年(37歳)後宇多天皇死去。正中の変。
1326年(39歳)邦良親王が急死する。
1331年(44歳)元弘の変。笠置山で挙兵、捕らえられる。
1332年(45歳)隠岐に流される。護良親王が挙兵する。
1333年(46歳)隠岐を脱出する。鎌倉幕府が滅亡する。帰京、光厳天皇廃位。
1334年(47歳)建武に改元
1335年(48歳)中先代の乱。足利尊氏、建武政権に反旗。新田義貞に尊氏討伐を命ずる。
1336年(49歳)建武の新政が崩壊する。吉野に脱出(南北朝時代の始まり)。
1339年(52歳)崩御
鎌倉幕府を滅ぼすも足利尊氏と対立して南朝を開く
後醍醐天皇は、第91代後宇多天皇の第二皇子として誕生しました。
諱を尊治といいます。
一代限りの天皇のはずだった
後醍醐天皇の即位は、当初から約束されていたものではありませんでした。
ところが後宇多天皇の第一皇子・後二条天皇が突然亡くなり、後醍醐天皇に出番が回ってきたのです。
とはいえ、後宇多天皇は孫の邦良親王(後二条天皇の皇子)を皇位に就かせたいと考えていました。
後醍醐天皇は、いわば「中継ぎ」としての役割を期待されたのです。
そして後宇多天皇はこのことについて、鎌倉幕府の了解も取り付けていたとみられています。
しかし後醍醐天皇は、これに黙ってはいませんでした。
後醍醐天皇の即位から3年、父・後宇多天皇が院政を停止します。
これは後宇多天皇が自ら停止したのではなく、後醍醐天皇が圧力をかけたとも言われています。
また父・後宇多天皇だけでなく、怒りの矛先は鎌倉幕府にも向けられました。
二度失敗した倒幕のクーデター

そこで後醍醐天皇は鎌倉幕府を倒そうと倒幕の計画を立てますが、幕府側にバレてしまいます。
しかし、側近の日野資朝らが処分されただけで、後醍醐天皇は何の処分も受けませんでした。
この出来事を「正中の変」と呼びます。
邦良親王が急死すると、再び皇位継承問題が浮上。
後醍醐天皇は自分の息子に譲位しようとしますが、
幕府側は両統迭立のルールに従い、持明院統の量仁親王(のちの光厳天皇)を皇太子としました。
なお、両統迭立については下記の記事で紹介しています。
これを不服とした後醍醐天皇は、再び倒幕を企てます。
武力を集めたり、僧に倒幕のための祈祷を行わせたりしました。
しかし、またもや倒幕計画が幕府側にバレてしまいます。
側近の日野俊基や祈祷を行った僧・文観らが捕えられ、後醍醐天皇にも追手が迫りました。
先手を打った後醍醐天皇は、三種の神器を持って京を脱出。
そして現在の京都府相楽郡笠置町にある笠置山で挙兵しました。
これに呼応し、後醍醐天皇の皇子・護良親王は大和で、さらに楠木正成は河内でそれぞれ挙兵しています。
しかし笠置山は幕府軍の手に落ち、後醍醐天皇は捕らわれの身になりました。
この出来事を「元弘の変」と呼びます。
流罪から倒幕へ
側近たちは死罪となりましたが、後醍醐天皇自身は隠岐に流されることに。
こうして不遇の時代を送ることになったものの、各地では倒幕の機運が高まっていきました。
そのような状況の中、後醍醐天皇は隠岐を脱出することに成功したのです。
現在の鳥取県にある船上山で挙兵した天皇は、倒幕の綸旨を発します。
すると幕府側として戦っていた足利尊氏が一転、倒幕側に加わることに。
その後尊氏は、京都の六波羅探題(幕府の出先機関)を攻め落としました。
また関東では新田義貞も挙兵し、あっという間に鎌倉を攻略。
およそ150年続いた鎌倉幕府を滅亡させました。
「建武の新政」と足利尊氏との対立

京に戻った後醍醐天皇は、鎌倉幕府によって擁立された光厳天皇を廃します。
そして天皇自らが政治を行う「建武の新政」をスタートさせました。
しかしこの政治は公家や寺社を優遇するものであったため、武士たちは不満を募らせるようになります。
そして遂に、足利尊氏が建武政権から離反。
天皇は新田義貞に尊氏の討伐を命じ、各地で戦いが繰り広げられました。
足利軍は新田義貞や楠木正成ら後醍醐天皇側の軍を圧倒。
後醍醐天皇は三種の神器を取り上げられ、尊氏は代わりに持明院統の光明天皇を即位させます。
そして後醍醐天皇は、花山院(※)に幽閉されることになりました。
※ 現在の京都御苑内にあった邸宅のこと
南北朝時代の始まり
花山院から密かに脱出した後醍醐天皇は、現在の奈良県・吉野へと逃れます。
そして自らの皇位の正統性を主張。
ここに、およそ半世紀続くことになる南北朝時代が始まります。
ですが病に倒れた後醍醐天皇は、吉野の地で亡くなりました(享年52歳)。
後醍醐天皇にまつわるエピソードや伝説
それでは後醍醐天皇にまつわるエピソードを紹介していきます。
日本史上有名な無礼講

お酒の席で、「今夜は無礼講で」なんて言ったりすることがあります。
無礼講とは身分の上下は関係なく、堅苦しい礼儀は抜きにして行う宴会のこと。
これを鵜呑みにして、羽目を外しすぎてしまう人もいますが……。
そんなことはさておき、後醍醐天皇が催した無礼講は日本史上有名な無礼講なのです。
その無礼講が行われたのは、後醍醐天皇が倒幕を企てていたときのこと。
幕府への批判をそれとなく口にし、信頼できる武将を物色して味方に引き入れるためでした。
一見は楽しいお酒の席ですが、実はとんでもない陰謀だったようです。
「今夜は無礼講」と聞いたら、少し警戒してみるのも良いかもしれません。
悲劇の皇子・護良親王
後醍醐天皇には少なくとも36人の子(うち皇子は18人)がいたとされています。
鎌倉幕府の倒幕でも活躍した、護良親王もその一人。
建武の新政では、征夷大将軍や兵部卿に任命されました。
1334年10月、護良親王は足利尊氏によって捕らえられます。
これは一説によると、尊氏を恐れた後醍醐天皇がその要求に従ったから、とされています。
その後護良親王は、鎌倉にあった東光寺の土牢に幽閉されることになりました。
そして翌年、鎌倉で中先代の乱が起こります。
そのどさくさに紛れ、尊氏の弟・直義の命を受けた家臣によって殺害されました。
幽閉中の護良親王は、
武家(尊氏)よりも君(父天皇)のうらめしく渡らせ給ふ(「梅松論」)
(引用:コトバンク「護良親王」https://kotobank.jp/word/護良親王-16980)
と漏らしていたと伝わっています。
なお明治維新後、親王を弔うため、東光寺跡に「鎌倉宮」という神社が創建されました。
これは明治天皇の勅命によるもので、その名前も明治天皇自らが付けたものです。
きょうのまとめ
今回は後醍醐天皇の生涯について、簡単にまとめました。
後醍醐天皇とは?
① 中継ぎとして即位し、鎌倉幕府に不満を持ったため倒幕を決意した
② 倒幕のクーデターは二度失敗して、隠岐に流された
③ 足利尊氏・新田義貞らの活躍によって、鎌倉幕府を滅亡させた
④ 建武の新政は失敗に終わり、足利尊氏と対立した
⑤ 吉野に脱出し、南朝を開いた
⑥ 無礼講で倒幕に協力してくれる武将を物色した
⑦ 息子・護良親王を足利尊氏に引き渡した?
こちらのサイトでは、他にも歴代天皇についてわかりやすく書いています。
より理解を深めたい方は、ぜひお読みになってください。
その他の人物はこちら
鎌倉時代に活躍した歴史上の人物
関連記事 >>>> 「【鎌倉時代】に活躍したその他の歴史上の人物はこちらをどうぞ。」
時代別 歴史上の人物
関連記事 >>>> 「【時代別】歴史上の人物はこちらをどうぞ。」

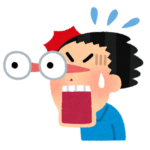
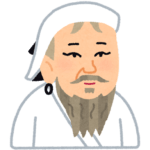
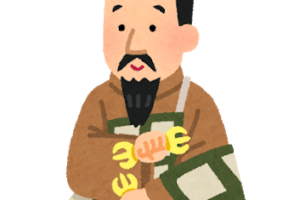


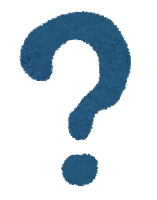
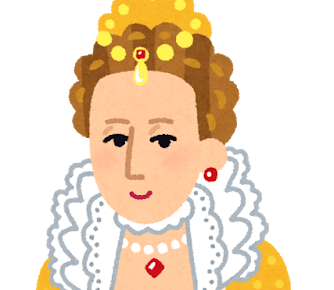


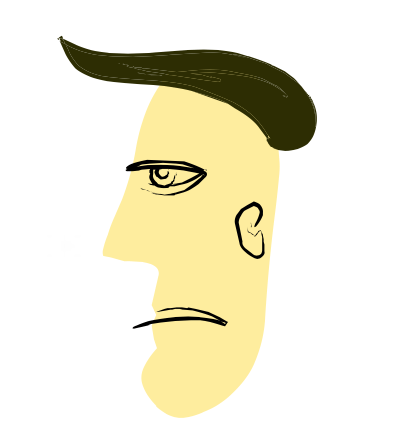
コメントを残す