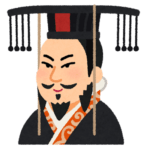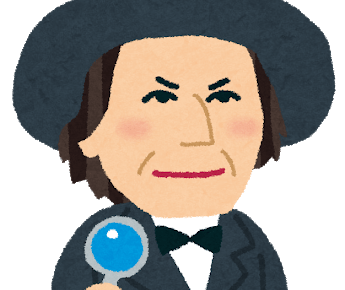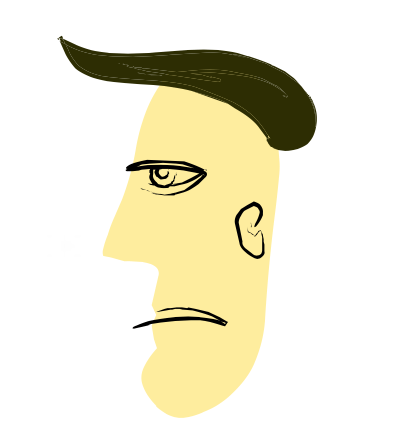大正の世において、これまでにないまったく新しい形の詩を提示した詩人として、次代の寵児となった
萩原朔太郎。
その作風は現代の詩の原型となっており、「日本の近代詩の父」とも名高い人物です。
『世界の中心で愛を叫ぶ』の主人公、松本朔太郎の由来になっていたり、
『ゲド戦記』の挿入歌『テルーの唄』は、朔太郎の詩『こころ』から着想を得たという話があったり…
最近でも何かと話題になることが多い人なんですよ。
そんな感じで、現代にも多大な影響を及ぼし続ける萩原朔太郎。
いったいどんな人物なのでしょう?
今回はその生涯を辿りましょう。
タップでお好きな項目へ:目次
萩原朔太郎はどんな人?

- 出身地:群馬県東群馬北曲輪町(現・前橋市千代田町)
- 生年月日:1886年11月1日
- 死亡年月日:1942年5月11日(享年 55歳)
- 文語体中心だった詩壇において「口語自由詩」を確立し、現代に続く詩のスタイルを確立した詩人。青少年期の経験から、どこか陰鬱とした詩を詠む。
萩原朔太郎 年表
西暦(年齢)
1886年(1歳)群馬県東群馬北曲輪町(現・前橋市千代田町)にて、開業医の父・萩原密蔵、母・ケイの長男として生まれる。
1900年(14歳)群馬県師範学校付属小学校を卒業。旧制前橋中学校(現・前橋高校)へ入学する。従兄の萩原栄次から短歌を教わり、校友会誌などで作品を発表した。与謝野晶子の『みだれ髪』に多大な影響を受ける。
1903年(17歳)与謝野鉄幹が主宰する新詩社の文芸誌『明星』に短歌を投稿し、新詩社同人となる。学業には集中できず、前橋中学校を落第。
1908年(22歳)熊本の第五高等学校へ浪人して入学するも1年で落第。
1910年(24歳)岡山の第六高等学校へ転入するも、また1年で落第。慶応義塾大学予科へ進むが直後に退学。
1911年(25歳)慶応義塾大学に再入学するも精神的な理由から中途退学。音楽教育者・比留間賢八からマンドリンを習い、音楽に目覚める。
1913年(27歳)詩人・北原白秋主宰の詩誌『朱欒』に詩を投稿。詩の掲載を通して作家・室生犀星と無二の親友となる。
1914年(28歳)前橋へ帰郷。生家の味噌蔵を書斎に改装する。室生犀星、山村暮鳥らと「人魚詩社」を設立。
1915年(29歳)詩誌『卓上噴水』を創刊。「ゴンドラ洋楽会」を結成し、マンドリン講師や演奏会の開催をする。
1916年(30歳)自宅にて週一回「詩と音楽の研究会」を開催。室生犀星と雑誌『感情』を創刊。
1917年(31歳)処女詩集『月に吠える』を自費出版にて刊行。作家・森鴎外らから絶賛され、詩壇での地位を確立。
1919年(33歳)上田稲子と結婚。
1923年(37歳)詩集『青猫』を刊行。
1925年(39歳)妻子を伴って上京。室生犀星、芥川龍之介らと親交を深める。故郷への想いを表現した詩集『純情小曲集』を刊行。
1927年(41歳)三好達治、堀辰雄、梶井基次郎らを門下生とし、後進の指導に力を入れ始める。
1929年(43歳)妻・稲子と離婚。翌年、父・密蔵の死と不幸が相次ぐ。
1931~1933年(45~47歳)万葉集、古今集の和歌を解説した『恋愛名歌集』の刊行、雑誌『生理』にて与謝蕪村、松尾芭蕉の評論を発表するなど、古典に傾倒していく。
1934年(48歳)詩集『氷島』を刊行。古典に影響を受けた作風が物議を醸す。明治大学にて詩の講義を担当するようになる。
1935年(49歳)小説『猫町』を刊行。
1937年(51歳)島崎藤村、戸川秋骨、武者小路実篤らと共に「北村透谷文学賞」の選考委員となる。
1938年(52歳)「新日本文化の会」の機関紙『新日本』を創刊。『日本への回帰』を発表し、日本主義者と批判を受ける。二人目の妻・大谷美津子と結婚。
1942年(55歳)体調不良から明治大学講師を辞任。同年5月11日、急性肺炎で没する。
青少年期
1886年、萩原朔太郎は群馬県東群馬北曲輪町(現・前橋市千代田町)にて、開業医の父・萩原密蔵と、母・ケイの長男として生まれます。
朔太郎という名前は誕生日が11月1日だったため、1日を意味する「朔日」から付けられたものです。
父・密蔵は東大医学部を首席で卒業した超が付くエリート。
朔太郎は長男であると同時に、兄妹では唯一の男子だったこともあり、跡取りとして多大な期待を込めて育てられることとなります。
しかし…そんな父の想いに応えることはできず、青少年期は苦悩に苛まれたものとなるんですよね…。
幼少期のトラウマ
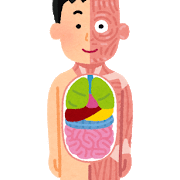
事件は朔太郎が6歳のころ。
生家にて一人で遊んでいたときに、うっかり父の医務室に迷い込んでしまったことがあったといいます。
そのとき父・密蔵が行っていたのは、こともあろうに遺体の解剖でした。
6歳の子どもがそんな現場に出くわす時点で十分にショッキング。
ところが密蔵はなんと、これを息子に医療のいろはを教えるチャンスだと受け取り、遺体から取り出した臓物を見せつけ、つぶさに説明をし始めたのだとか。
この出来事がトラウマになった朔太郎は塞ぎこみ、父の望む医学の道にはことさら拒絶反応を示すようになります。
度重なる落第

朔太郎は群馬県師範学校附属小学校を首席で卒業。
それほどの才児でした。
にも関わらず、高校は転入と落第を繰り返すこととなります。
学校へ行くと嘘をついては森を散歩していたりするし、授業に出ても窓の外ばかり見て上の空。
試験もろくに受けようとしない。
こんな感じの授業態度から、学校を中途退学した回数は計5回にも上ります。
どうしても、学問には積極的になれなかった朔太郎。
やはり幼少期のトラウマが響いているのでしょうか…?
最終的には慶応義塾大学予科に入学するものの、その年に退学し、学問を完全に諦めてしまいます。
これは岡山の第六高等学校の教師が
「朔太郎に学問の将来性なし」
と、父・密蔵に報告したことが原因だったという話も。
こういった経緯から、以降、朔太郎は父との関係に深い影を落とすこととなるのです。
詩と音楽が朔太郎の救いだった?
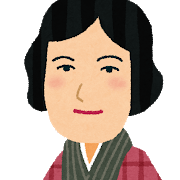
学問はからっきしダメでしたが…朔太郎が学校に通うかたわら、熱中したものが詩と音楽でした。
旧制前橋中学(現・前橋高校)に通っていたころ、生家をよく訪ねてきていた従兄・萩原栄次から短歌を習い、校友会誌などで作品を発表するように。
特に夢中になったのが与謝野晶子の『みだれ髪』で、朔太郎はこのころを回想し
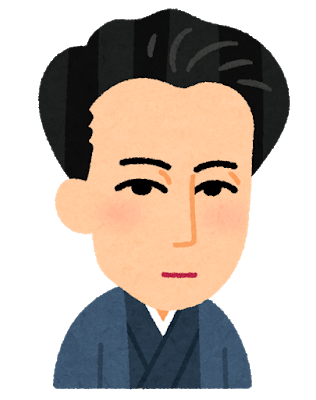
と記述しています。
このあとすぐ、晶子が作品を掲載していた文芸誌『明星』にも短歌を投稿していることから、その熱中度合いは明らかです。
そして音楽も、朔太郎にとっては詩と同じような位置付け。
朔太郎は学校での対人関係もあまり得意ではなく、小学校時代はハーモニカやアコーディオンに興じることで孤独を紛らわせていたのだとか。
慶応義塾大学予科に通っていたころには、音楽教育者・比留間賢八からマンドリンを習ったりもしました。
後年、朔太郎が結成、指導を務めた「ゴンドラ洋楽会」は、群馬交響楽団の源流になったともいわれていますよ。
詩と音楽はいずれも、自身の内なる感情を表現するもの。
朔太郎は人並外れた感性をもって、その両方で才覚を表していたわけです。
詩壇デビュー
大学を中退した朔太郎は、このあと27歳のころ、北原白秋主宰の詩誌『朱欒』にて、本格的に詩壇デビューを果たすこととなります。
なんといってもこのころの朔太郎の詩は、始まって以来の革命を詩壇へともたらすことになるのです。
北原白秋、室生犀星との出会い

朔太郎が『朱欒』へ詩の投稿をすることを決めたのは、同紙にて北原白秋や、詩人・室生犀星の作品にいたく感動したためでした。
そのぐらい感性に惹かれるものがあったためか、彼らと朔太郎は友人としても無二の仲になっていきます。
白州や犀星との逸話を聞いていると、詩との出会いが確実に朔太郎の人生を豊かにしていったことが伺い知れますよ。
詩の投稿を通じ、白秋とは共に銭湯へ行くほどに。
犀星とも文通を経て実際に会うようになり、親友となっています。
犀星が前橋を訪れた際は、朔太郎が宿代を全額持ったという話も。
飲み屋に行くときだって、いつも朔太郎のおごりです。
学生時代、朔太郎はいつも一人でしたが、それは同じような芸術的感性をもつ人が側にいなかったこともあるのでしょうね。
ちなみにいうと、朔太郎と犀星の第一印象は、お互い決してよくはなかったという話で…
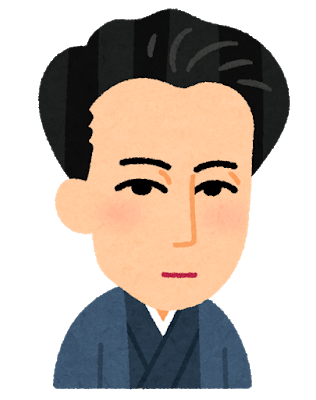

みたいな感じだったとか。
ここから親友になってしまうなんて、どこぞの漫画にでも出てきそうなストーリーですよね!
口語自由詩の確立

『朱欒』にて詩人の道を歩み始めた朔太郎は31歳のころ、ついに自身初の詩集を刊行することとなります。
これが朔太郎の代表作としてよく知られている『月に吠える』です。
朔太郎はこの詩集において、今までにないまったく新しい詩の形を提示し、詩壇に革命を起こすこととなります。
それまでの日本の詩というのは、和歌などによく見られる文語体を用いたものが主流でした。
(※文語体…古来から使われている書き言葉。「~なり」「~れり」「~で候」とか、そういうヤツ。)
これに対し、朔太郎が『月に吠える』で記したのは、「口語自由詩」。
それまでの詩は俳句の五七五のように、ある程度決まった音数がありましたが、朔太郎はそういったルールを一切設けない自由な形で詩を書いたのです。
用いた文体は現代の話し言葉に近い口語。
想像するとわかるように、現代の詩はほとんどがこの口語自由詩の形式で書かれていますよね。
実はそのパイオニアが朔太郎(すげえ!)で、そのために彼は「日本近代詩の父」という異名をもっているのです。
『月に吠える』は作家・森鷗外などが絶賛したことにより、瞬く間に完売。
読者の希望により後年、再版されるほどの人気を得ました。
ちなみに実はこの『月に吠える』は一時、内務省から発禁処分を受けるピンチにもさらされています。
人の死や病気などを大々的に扱っているため、風紀を乱すと見られてしまったためです。
結局は室生犀星の協力で、二編の詩を削除することで刊行できることに。
再版時にはその二編の詩も載せているため、朔太郎としては発禁処分を受けたことにも納得がいっていなかったようです。
例として一部分紹介してみると、こんな詩もあります。
あふむきに死んでゐる酒精中毒者の、
まつしろい腹のへんから、
えたいのわからぬものが流れてゐる、
透明な青い血漿と、
ゆがんだ多角形の心臓と、
腐ったはらわたと…出典:月に吠える/酒精中毒者の死
…たしかにちょっと刺激が強すぎるような気もしますね。
深まる父との確執

『月に吠える』の刊行をもって、朔太郎には認めてもらいたい相手がひとりいました。
父・密蔵です。
密蔵の期待に応えられず、落第を繰り返してしまった学生時代。
挙句、詩人として芽が出せる31歳になるまで、朔太郎は働きもせず、ただただ詩作にふけるニートのような暮らしをしていたわけです。
後ろめたい気持ちはあるし、早く結果を出して密蔵に報告したい。
詩壇で「まったく新しい形の詩だ!」と認められた『月に吠える』なら、それが叶う。
父もきっと認めてくれると、朔太郎は思っていたわけですね。
しかし、朔太郎がこの詩集を見せたことで、密蔵との確執はさらに深まってしまうこととなります。
前述のとおり、『月に吠える』は人の死や病気を大々的に扱った詩集です。
医師である密蔵にとって、それらは立ち向かうべき敵。
その内容に激怒した密蔵はなんと、詩集を朔太郎の目の前で燃やしてしまうのです…。
世間からいくら絶賛されようとも、父だけは認めてくれない。
『月に吠える』には、そんな自身の在り方に悩む心情を描いたような、こんな詩も載せられています。
みんなそつとしてくれ、
そつとしてくれ、
おれは心配でたまらない、
たとへどんなことがあつても、
おれの歪んだ足つきだけは見ないでおくれ。
おれはぜつたいぜつめいだ、
おれは病気の風船のりみたいに、
いつも憔悴した方角で、
ふらふらふらふらあるいてゐるのだ。出典:月に吠える/危険な散歩
妻・稲子との関係
朔太郎は1919年に一人目の妻・上田稲子と結婚。
長女の葉子、次女の明子をそれぞれ設けています。
しかし稲子との結婚生活は約10年で破綻を迎えることに。
朔太郎はその理由として
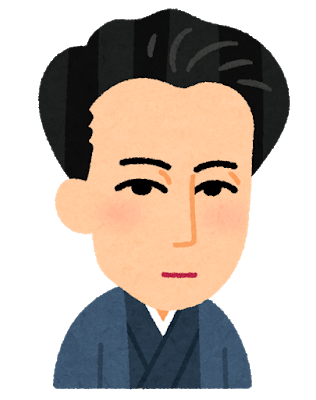
という理由を挙げていますが、実際のところは彼が妻よりも自身の妹たちを大事にし過ぎたがゆえという話もあります。
なんでも萩原家は嫁いできた嫁に当たりが強く、朔太郎の母や三人の妹たちはこぞって稲子を攻撃したという話。
朔太郎はこれを見てみぬふりをし、妻を庇うことは一切なかったといいます。
室生犀星や芥川龍之介らと軽井沢へ旅行に行った際も、妻ではなく妹のユキとアイを連れて行ったという話も…。
ただ、これを見て朔太郎をシスコンのろくでなしとするのはちょっと待って欲しいんです。
室生犀星はエッセイ『我が愛する詩人の伝記』のなかで、朔太郎とその妻との関係を語っています。
その内容を見ると、朔太郎は稲子を大事にしていなかったわけではないんじゃないの?と、思わされるんですよね。
朔太郎は妻を叱るようなことは一度もなく、いつも温和に接していたといいます。
別れるときだって稲子が別の男性と駆け落ちをしたにもかかわらず、ちゃんとお金を渡していますし…。
こういったことからきっと、朔太郎は妹びいきだったというより、人に対してはっきり意見を言うのが苦手だっただけなんじゃないかな?と、私は想像しています。
妹に対しても妻に対しても、朔太郎が何も言えなかったがゆえ、パワーバランスの強い妹たちに稲子が押し負けることになってしまったんじゃないかな?…と。
何が本当かはわかりませんが、子どものころから塞ぎがちな朔太郎の性格を考えると、こういう想像に行き着くんですよね。
ちなみに二人目の婦人・美津子も
「今考えると何故離婚したのかよくわからないほど、萩原はいい人だった」
と語っています。
朔太郎はいずれの妻に対しても、きっととても優しい旦那だったはずです。
古典への回帰

晩年になると朔太郎は、万葉集や古今集の解説、松尾芭蕉など、江戸時代の俳人の評論などを発表を通し、だんだんと古典に傾倒していきます。
極めつけは1934年刊行の詩集『氷島』。
朔太郎の詩が注目を浴びたのは、前述のとおり、これまでにない口語自由詩という形式を確立したためでした。
しかしこの『氷島』の詩は、なんと全編文語体で書かれているのです。
以下は『氷島』に収録されている『遊園地にて』の冒頭部分
遊園地の午後なりき
楽隊は空に轟き
回転木馬の目まぐるしく
艶めく紅のゴム風船
群集の上を飛び行けり。出典:氷島/遊園地にて
「るなぱあく」というのは、前橋市に現存する遊園地です。
回転木馬(メリーゴーランド)、ゴム風船という近代的な描写に関わらず「~なりき」「~けり」などと、平安貴族が使っていそうな古めかしい言葉遣いが登場していますね。
これがいわゆる文語体。
そう、朔太郎はこの『氷島』で、古典への回帰をしているのです。
この試みは当時物議を醸し、
と、評価する人も少なくありませんでした。
個人的には、現代の風景を昔の言葉で描いているところに新しさすら感じるのですが…。
時代は昭和に入り、日本の世情はどんどん欧米化へと向かっていました。
そんな時勢において、朔太郎は古きよきものの魅力を忘れてしまった人々へ、作品を通した訴えかけをしていたのかもしれません。
このあと1938年には、新日本文化の会の機関紙『新日本』にて、『日本への回帰』という文章を発表。
さらに自身の立ち位置を明確にし、欧米化を推し進める政府に反発する思想の持ち主だと批判を受けたりもしました。
日本の欧米化は海外諸国との戦争を視野に入れたもの。
そういう事情があると、何を正解とするかは難しいですよね。
欧米の文化も日本古来の文化も、どちらも個性があっておもしろい。
そう捉えられるのは、私たちが平和な時代に生きているからこそなのでしょう。
きょうのまとめ
エリート医師の家系に生まれながら、学問はからっきしダメだった萩原朔太郎。
しかし詩の才能は、詩壇始まって以来の革命を起こすほどのものでした。
全然ダメに思えても、人には必ず才能を発揮できる分野があるものです。
それを見つけるためには、朔太郎のように、やったことのないさまざまなものに挑戦していく姿勢が大事なのでしょうね。
最後に今回のまとめです。
① 学生時代の萩原朔太郎は計5回の落第を繰り返し、学問を諦めてしまった。学びに積極的になれなかったのは、幼少期に父の医務室で遺体解剖を見たトラウマから?
② 詩と音楽が救いだった朔太郎は、北原白秋の詩誌『朱欒』にて本格的に詩壇デビュー。処女詩集『月に吠える』でそれまでにない「口語自由詩」を確立し、詩壇の寵児となった。
③ 晩年は古今集や万葉集を始めとする古典からの影響が見られた。文語体で書かれた詩集『氷島』は「退化した」と批評されることも。欧米化へ向かう日本への問題定義だった?
だからこそ、人とは違う感性の詩が詠めたともいえますが…。
ただ、友人関係など恵まれた部分も少なからずあるため、実際のところ、幸せは十分に感じていたのかも。