どんなに文学に疎い人でも、大正の大文豪・芥川龍之介の名前を聞いたことがない人はそうそういないでしょう。
代表作の『羅生門』などは中学の国語でも習いますし、『蜘蛛の糸』などの童話もテレビで放映されていたりするので、多くの人がどこかで作品に触れているはず。
そうでなくても、現代の日本文学界において「芥川賞」はトップクラスの栄誉として知られています。
このように現代人も何かと接することの多い芥川龍之介ですが、著名な作家という以外のことは、実はみんな知らないのでは?
いったい彼はどんな人物だったのでしょう。
芥川というと、人間の本質をついたような、闇を感じさせる作品が主流です。
その生涯を辿ると、いかにしてその感性が育っていったのかも垣間見えますよ!
以下より詳しく見ていきましょう。
タップでお好きな項目へ:目次
芥川龍之介はどんな人?
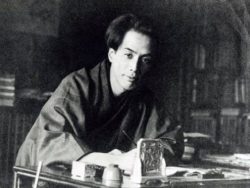
芥川龍之介
出典:Wikipedia
- 出身地:東京市京橋区(現在の東京都中央区)
- 生年月日:1892年3月1日
- 死亡年月日:1927年7月24日(享年35歳)
- 「芥川賞」で有名な大正時代屈指の短編作家。人間の闇を描いた作風が主流
芥川龍之介 年表
西暦(年齢)
1892年(1歳)東京市京橋区(現在の東京都中央区)にて牛乳製造業を営む父新原俊三・フクの長男として誕生。生後7か月でフクの病気のため、母方の芥川家に預けられる。
1903年(11歳)母フクが亡くなり、正式に芥川家の養子に。
1910年(18歳)府立第三中学校卒業。「多年成績優等者」の賞状を受け、第一高等学校第一部乙類に無試験で入学。
1913年(21歳)東京帝国大学(現在の東大)英文学科に入学。
1914年(22歳)高校時代の同期である菊池寛・久米正雄らと同人誌『新思潮』を刊行し、作家活動を開始。
1915年(23歳)代表作『羅生門』を文芸誌『帝国文学』にて発表。
1916年(24歳)『新思潮』にて発表した『鼻』を師匠の夏目漱石が絶賛。大学を20人中2番目の成績で卒業し、海軍機関学校の英語教師に。
1917年(25歳)短編集『羅生門』『煙草と悪魔』を刊行。教師のかたわら、小説執筆の仕事。
1919年(27歳)英語教師を辞職、大阪毎日新聞社に入社。塚本文と結婚。
1921年(29歳)海外視察員として中国へ派遣される。神経衰弱や腸カタルなど、体調を崩す。
1925年(33歳)文化学院文学部講師に就任。
1927年(35歳)睡眠薬を大量に摂取、自宅にて自殺。
芥川龍之介の幼少期
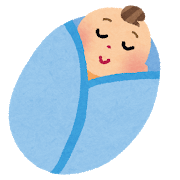
芥川龍之介は1892年、東京市京橋区(現在の中央区)にて、牛乳製造業を営む父・新原敏三と母・フクの長男として誕生します。
ここで「新原?じゃあ芥川は本名じゃないの?」と思った人もいるかもしれません。
芥川龍之介はれっきとした本名で、これも彼を取り巻いた複雑な家庭環境を物語るものです。
両親の温もりを知らずに育った幼少期
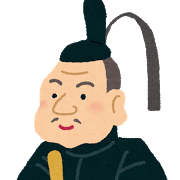
実は芥川は生後7か月で母のフクが精神病を患ったため、母方の芥川家に預けられることになりました。
なんでもフクの病気は相当にひどく、芥川の面会もままならない状態だったとか。
そのため彼は母親の温もりというものを一切知らずに育ったわけです。
もちろん母親代わりをしてくれた伯母のフキも教育熱心で、大切にはしてくれました。
また芥川家は江戸時代、徳川家に仕えていた名残から芸術や演芸への理解が深く、このことも芥川の文人としての基礎に大きく影響しています。
芥川が勉強に没頭したのは見捨てられないように?
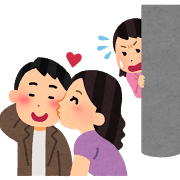
「なんだ…両親にこそ恵まれなかったけど、意外に悪くない環境じゃないか」と思った人もいるでしょう。
しかし芥川が11歳のころのこと、さらなる波乱が彼の身を襲います。
この年に母のフクは亡くなってしまいます。
そして同時期に父の敏三が伯母のフキと不倫をしていたことが発覚するのです。
これによって芥川家と新原家の仲は完全に悪化。
新原龍之介が芥川龍之介へと変わった瞬間でした。
芥川は幼少より成績優秀で、1913年には年に数人しか合格者が出ない東京帝国大学英文学科への入学も決めてしまうほどです。
これは一見、環境に左右されず努力してきたのだな…と感心させられる逸話です。
しかしひょっとすると「何かに秀でていないと、また同じように見捨てられてしまう」という恐怖からの努力だったのかもしれませんね。
作家としての活動をスタート
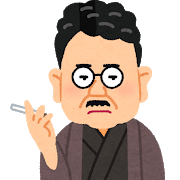
大学生になると芥川は友人の久米正雄・菊池寛らと同人誌『新思潮』の刊行を始めたことをきっかけに作家としての活動をスタートさせます。
作家としては早熟も早熟。瞬く間に名を挙げていった20代
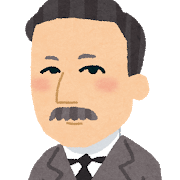
彼の台頭は早熟も早熟。
なんと代表作の『羅生門』はこの大学在学中、23歳のころの作品なんです。
…現代でも、この歳で教科書に載るような作品を発表できる人というのはまずいません。
また24歳のころに発表した『鼻』も、当時芥川が指示していた夏目漱石が絶賛したことで有名です。
さらに卒業後は一度、海軍機関学校の英語教師になります。
しかし執筆依頼が殺到したために辞職し、大阪毎日新聞社に入社して創作活動に専念します。
新聞社の社員なのに小説を書くことだけが仕事というのもすごいですね。
破竹の勢いとはこのことです。
やはり文人としての才覚は江戸より続く芥川家の家柄により、着々と磨かれていたということでしょうか。
古典を題材にした作品が多いこともその家柄と関係がありそうです。
恋愛が芥川の創作意欲に火をつけた?

才能を発揮しだした大学時代、芥川はひとつの大きな失恋も経験しています。
お相手は幼なじみで青山女学院英文科に通っていた吉田弥生という女性。
芥川は彼女との結婚を考えていたわけですが、芥川家の反対に遭い、結局諦める形になってしまいます。
彼女は家柄も悪くなければ、学力にしても芥川と釣り合いが取れていました…なのにどうして?
と思うところですが、これにもまた父の敏三が関係してきます。
そう、彼女の生家である吉田家は、敏三の新原家と仲が良かったのです。
新原家を毛嫌いしている芥川家としては、「そんな家の娘を嫁にもらうわけにはいかん!」となってしまったわけですね。
敏三さん…どこまで芥川の足を引っ張れば気が済むんだ…。
と言いたくなるところですが、彼の創作意欲に火が点いたのは、この失恋がきっかけだったとも考えられます。
そう、芥川が作品を次々と執筆しだしたのは、失恋を経たこの時期から。
彼女のために仕事を頑張ろうと思ったり、失恋の辛さを乗り越えるために何かに没頭したりという経験は覚えがある人もいるでしょう。
たしかに恋愛は絶大なパワーをもっていますよね。
芥川の作品5選
ここで芥川の作品を5つみていきましょう。
羅生門

国語の教科書にも載っている芥川の代表作『羅生門』です。
京都・平安京の衰退とともにボロボロになり、死体の遺棄場と化した羅生門。
その死体からカツラを作って売るためと、毛髪を引き抜く老婆。
終始陰鬱な作風はいかにも芥川節といったところでしょうか。
あらすじはというと、
「不景気の煽りで職を失った男が、ひとりの老婆とのやり取りを通して、生き抜くために盗人になることを決意するまでの心理」
を描いたものです。
路頭に迷っていた男は、ときに正義感を見せたかと思うと、ひょんなことから悪党へと様変わり。
人間の心持ちというのは、いざとなればこうも簡単に変わってしまうのか…と、考えさせられる、そんな作品です。
鼻
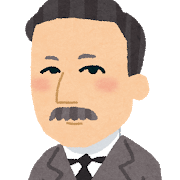
芥川は大学在学中、かの夏目漱石が主宰する”木曜会”という作家志望者の集まりに参加するようになりました。
その木曜会にて漱石が芥川の才能を見出し、絶賛したとされる作品が『鼻』です。
物語の主人公は禅智内供ぜんちないぐという、鼻の長さがアゴまで伸びている僧侶。
彼はその異様な鼻のせいで人から笑い者にされていましたが、ある方法を知り、鼻を短くすることに成功します。
しかし鼻が短くなると、それを見た人は長かったときよりもさらにおかしそうにする。
結局人々が内供を見て笑っていたのは、見てくれの問題ではなく、彼に不幸であってほしいから…という結末の話です。
他人の不幸は蜜の味…いかにもその言葉通りの物語ですね。
杜子春
ここまでの2作品はかなりどす黒い内容でした。
『杜子春』は芥川作品のなかでもちょっと珍しい、ハッピーエンドになっています。
物語の主人公は両親を早くに亡くし、財産も使い果たしてしまった杜子春という青年。
彼はあるとき途方に暮れていたところ、通りがかりの老人のアドバイスで莫大な富を得ます。
しかし杜子春はそこから何度も散財を繰り返し、そのたびに老人の助けを受けることに…。
そして莫大な富を得て、それをなくして…という経験から、杜子春はある気付きに辿り着きます。
決定打となったのは、老人の導きで亡き母の言葉を聞く機会を得たこと。
最後に杜子春が出した結論とは…?
人の幸せはお金や地位だけでは決まらない。そんな教訓を感じさせられる作品です。
猿蟹合戦
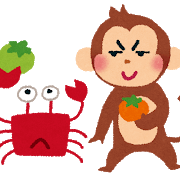
なんと芥川はおとぎ話の猿蟹合戦の続編を書いています。
…が、彼の作風から察するとおり、それはとても子ども向けとはいえない内容。
おとぎ話の猿蟹合戦は、蟹が猿をやっつけ、その後は幸せに暮らしたような雰囲気で終わっています。
しかし芥川の書いた続編では、蟹はこの後悲劇の道を辿ります。
しかもその結果になってしまった理由がまた、現実的すぎるほど現実的なのです。
そしてその蟹の運命を例に、多くの人がこの蟹と同じような境遇にあるという旨まで…。
つまりいくら正義を振りかざしたところで、報われないことは現実にもたくさんあるということでしょう。
そしてその正義というのも、結局は自分都合の正義でしかない…というようなことも感じさせられます。
やはり子どもに読み聞かせるにはちょっと早いかな…
といった感じですね。
河童

芥川が晩年の1927年に書き残した作品『河童』。
題名の通り、河童を題材にした物語です。
登場するのは”妖怪”というおどろおどろしいイメージのものではなく、どこかコミカルで憎めない河童たちです。
あるとき河童の世界に迷い込んでしまった主人公はそのままそこに住むことになり、河童たちのなかで社会生活を営んでいきます。
河童たちの暮らしはどこか人間社会の矛盾を皮肉るような風合いもあるけど、やはり彼らはどこか憎めない。
これだけを聞けば、なんだか子ども向けアニメにでも出てきそうな微笑ましい設定ですが、
そこはやはり芥川作品。
主人公が迷い込んだ河童たちの世界は実は…?
という、ある種の狂気を思わせるオチが用意されています。
波乱を極めた晩年

芥川は自殺という悲劇的な死を遂げます。
ここまでを追ってみると、幼少期はともかく、作家になってからはかなり順調な人生のようにも思えます。
しかし晩年の彼の人生はそりゃあもう、自殺するのもおかしくないぐらい壮絶です。
まず芥川は27歳のころ、友人の紹介で塚本文という女性と結婚しているのですが、文は芸術に対して無関心なところがあり、夫婦仲があまりうまくいきませんでした。
そのせいもあって芥川は、秀しげ子という女性と不倫をます。
しかし、しげ子は芥川の弟子にも手を出していたのだとか。
芥川はそれきりで彼女との関係を切りますが、諦めきれないしげ子は
「芥川の子を身ごもっている」と言い出す始末。
このころから芥川が体調を崩し始めたのは、しげ子との関係を巡る心労からでしょう。
そして
・胃潰瘍
・神経衰弱
など、体調も一向に優れない晩年、1927年のこと、義理の兄・西川豊が保険金詐欺の疑いをかけられて自殺します。
この際、西川の残した借金や、姉の生活費も芥川が工面しなければならず、彼は文字通り馬車馬のごとく働かなければいけませんでした。
このように立ち行かなくなってしまった自分の人生に嫌気がさした芥川は同年、睡眠薬を大量に摂取し、35年という短い人生に終止符を打つのです。
ちなみにこの年もギリギリまで『河童』『歯車』など、著名な作品を出し続けています。
芥川龍之介は人生に希望こそ見出せませんでしたが、生涯作家であり続けたのですね。
きょうのまとめ
芥川龍之介が35歳という若さで亡くなったことは有名な話ですが、その生涯を辿ると、彼が作家として活躍した時期の短さにもまた驚かされます。
23歳の『羅生門』が始まりと考えると、わずか10数年。
名作とされる作品の多さを考えると、どれだけ研ぎ澄まされた感覚で、ひとつひとつが作られていたのかを痛感させられます。
そしてその才能を支えていたのは波乱に満ちた人生そのものだと言わざるを得ないでしょう。
…なんだか皮肉な話です。
最後に今回のまとめをしておきましょう。
① 芥川龍之介は幼少期、両親の温かみを知らずに育ったが、その反動で勉学に励んだ
② 大学時代は『羅生門』『鼻』などの名作を続々と生み出し、一気に名を挙げていく。あの夏目漱石も絶賛した
③ 晩年は女性問題や親族の自殺、生活苦などを抱え、精神をすり減らしていった
人間社会を生きていくうえで、「苦しみ」「闇」といった部分は、誰しもが突き当たる壁です。
それを痛いぐらいに経験し、現代に残した芥川龍之介。
その作品に触れておく価値は大きいですね。
目次に戻る ▶▶
その他の人物はこちら
明治時代に活躍した歴史上の人物
関連記事 >>>> 「【明治時代】に活躍したその他の歴史上の人物はこちらをどうぞ。」
時代別 歴史上の人物
関連記事 >>>> 「【時代別】歴史上の人物はこちらをどうぞ。」
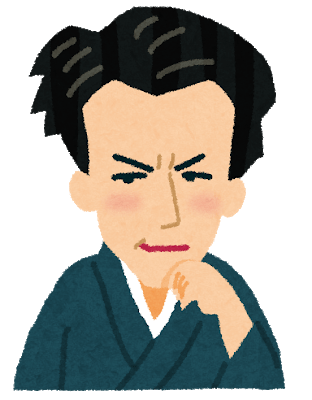



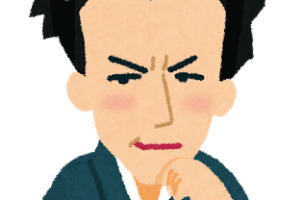

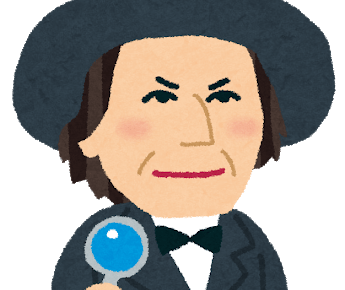


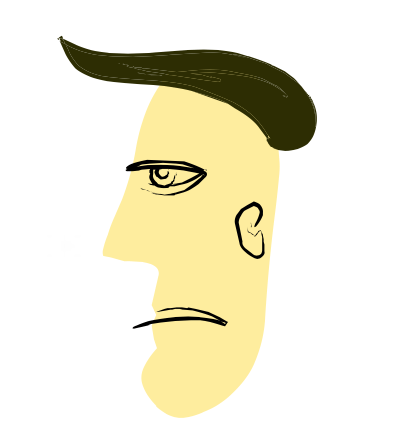
事実は、かなりねじ曲げられている。
調べて良かった。
私は、遠藤周作の遺作となった『影に対して』を読み
考えさせられる。
陰と陽は、誰にでも有りうるもの
これは後世に伝えていくべきものかと推察する。
コメントありがとうございます!