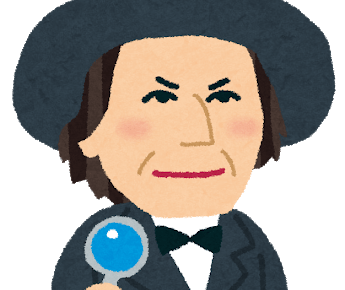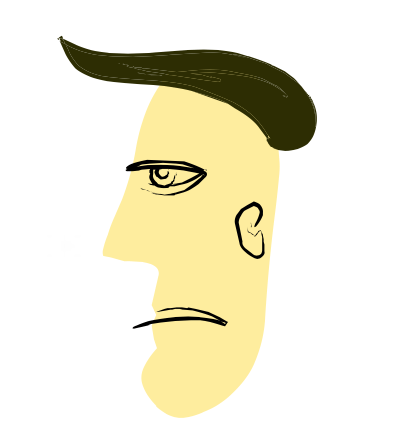明治末期~昭和中期までという、かなりの長期間を前線で活動し続けた
作家・谷崎潤一郎。
その作風は女性崇拝、風俗、マゾヒズムなどの危なっかしいテーマを扱っており、当時としては類を見ない内容でした。
また潤一郎は扱っているテーマが注目されただけでなく、その文章構成も芸術性が高いと評価される人物。
晩年には日本人で初めてノーベル文学賞候補にノミネートされるなどの偉業も残しています。
そんな谷崎潤一郎はどんな人物だったのか、今回はその生涯を通して辿りましょう。
その生活のほとんどが作品の糧となっていることに驚くはずですよ。
タップでお好きな項目へ:目次
谷崎潤一郎はどんな人?

1951年に撮影
出典:Wikipedia
- 出身地:東京市日本橋区蛎殻町(現・中央区日本橋人形町)
- 生年月日:1886年7月24日
- 死亡年月日:1965年7月30日(享年79歳)
- 大正、昭和の日本を代表する小説家。風俗、マゾヒズムといった非現実を主題とし、流行と一線を画す作風で注目された。文体にこだわりぬいた芸術性の高さに定評がある。
谷崎潤一郎 年表
西暦(年齢)
1886年(1歳)東京市日本橋区蛎殻町(現・中央区日本橋人形町)にて、父・谷崎倉五郎、母・関の長男として生まれる。
1897年(11歳)日本橋坂本小学校尋常科を卒業、高等科へ進学。高等科では恩師の影響で文学に目覚め、友人らと回覧雑誌『学生倶楽部』を刊行した。
1901年(15歳)家業の経営不振により進学を危ぶまれるが、恩師らの引き立てで家庭教師をして学費を工面。東京府立第一中学校(現・日比谷高等学校)へ進む。
1902年(16歳)校長の提案で二学年から三学年へ飛び級。三年でも首席の成績を修めた。
1905年(19歳)府立第一高等学校英法科へ進学。校友会雑誌にて小説を発表する。
1908年(22歳)東京帝国大学国文科へ進学。
1910年(24歳)小山内薫、和辻哲郎らと第2次『新思潮』を創刊。戯曲『誕生』、小説『刺青』『麒麟』などを発表する。
1911年(25歳)同人誌『スバル』に参加。文芸誌『三田文学』上で、作家・永井荷風の称賛を受け、文壇での地位を確立する。このころ学費未納により大学を中退。
1915年(29歳)芸者の石川千代と結婚。翌年、長女・鮎子が生まれる。
1917年(31歳)芥川龍之介、佐藤春夫との交流が始まる。千代の妹・せい子を養育することとなる。
1920年(34歳)横浜の映画制作会社・大正活映の脚本部顧問となり、せい子を女優デビューさせる。
1921年(35歳)妻・千代との関係を巡って佐藤春夫との関係が悪化(小田原事件)。
1923年(37歳)関東大震災の影響から関西へ移住。京都や兵庫などを転々とする。
1924年(38歳)せい子との関係をモデルにした小説『痴人の愛』を発表。
1927年(41歳)文芸誌『改造』にて芥川龍之介との論争が勃発。同年、芥川が自殺する。
1928年(42歳)妻・千代との冷めきった関係をモデルにした小説『蓼喰ふ蟲』を発表。
1930年(44歳)千代と離婚し、千代は佐藤春夫と再婚。3人の声明が発表され、「細君譲渡事件」として文壇を騒がせる。
1931年(45歳)大阪女子専門学校の女学生・古川丁未子と結婚。
1932年(46歳)兼ねてから惹かれていた人妻・根津松子の別荘へ転居。不倫が始まる。
1934年(48歳)丁未子と離婚。翌年には松子の離婚も成立し、三度目の結婚へ。『源氏物語』の現代語訳を始める。
1937年(51歳)帝国芸術院会員に選ばれる。
1939年(53歳)『源氏物語』の現代語訳を脱稿。
1943年(57歳)松子の姉妹4人をモデルにした小説『細雪』の連載を始めるも、戦時中の時勢にそぐわないと発禁処分を受ける。
1944年(58歳)『細雪』上巻を私家版として刊行。
1947年(61歳)『細雪』中巻を刊行。毎日出版文化賞を受賞する。
1948年(62歳)『細雪』下巻を刊行。翌年、朝日文化賞、文化勲章を受賞する。
1951年(65歳)『新訳源氏物語』を発表。文化功労者に選ばれる。
1958年(72歳)日本人初のノーベル文学賞候補となる。
1959年(73歳)高血圧症の影響で右手に麻痺が起こり、以後、秘書による口述筆記に移行する。
1963年(77歳)61年に発表した『瘋癲老人日記』により、毎日芸術賞を受賞。
1964年(78歳)アメリカ芸術文学アカデミー名誉会員となる。『新々訳源氏物語』を刊行。
1965年(79歳)東京医科歯科大学附属病院に入院。退院するも、腎不全、心不全を併発し、7月30日に死没する。
神童と呼ばれた少年期
谷崎潤一郎は1886年、東京市日本橋区蛎殻町(現・中央区日本橋人形町)にて、谷崎倉五郎、関の長男として生まれます。
先代から家業を継いだ谷崎家は大変裕福で、潤一郎はひとりでは小学校に登校もできないようなお坊ちゃん育ち。
そして特筆すべきは、彼が類を見ない神童だったということでしょう。
危ぶまれた進学。教師たちに惜しまれ解決

潤一郎が文学に目覚めたのは、彼が尋常小学校高等科へ進んだ11歳のころの話でした。
回覧雑誌『学生倶楽部』で作品を発表するようになった潤一郎は、その完成度の高さから、学内で注目を集めるようになります。
そんな評判が潤一郎を救う出来事が起こるのが、彼が小学校を卒業する15歳のころのこと。
谷崎家は先代によって財を成した事業家でしたが、実のところ、それを受け継いだ父・倉五郎には商才がなく、このころ廃業に追い込まれるピンチに陥っていました。
潤一郎の学費など当然払えるはずもなく、彼は進学を諦めざるを得ない状況に立たされていたのです。
しかしここで潤一郎の就職に待ったをかけたのが、その才能を惜しんだ教師たちでした。
彼らの奔走により、潤一郎は住み込みの家庭教師として働きながら進学できることに。
こうして無事、府立第一中学校へと入学するにいたるのです。
このとき、協力してくれた教師のなかには、潤一郎に文学の魅力を教えたといわれる恩師・稲葉清吉先生もいたといいます。
…で、これは余談ですが、潤一郎といえば恋多き男の印象をもっている人も多いはず。
実はその女性遍歴はこのころから始まっていて、なんと家庭教師をしていた家の女中と駆け落ちをする騒動も起こしています。
紹介した先生たちの面目が…という話はありますが、これもまた文豪らしいといえば文豪らしいのか…。
校長の勧めで飛び級
潤一郎の神童エピソードは、中学校へ進学した以降も続きます。
中学2年の一学期の話、潤一郎はあまりの成績の良さに、校長直々に3学年への飛び級を勧められるのです。
しかも飛び級した先でも成績は変わらず首席という秀才っぷり。
文学に傾倒していたかと思えば取り立ててそういうことでもなく、学業ならなんでもこなせたといいます。
このあと潤一郎は府立一高を経て、東京帝国大学国文科へと順調に進学。
成績を鑑みて周囲は法科を勧めたといいますが、潤一郎は自分の意向を尊重し、文学の道へ進むのです。
女性崇拝の思想は両親の影響?

潤一郎の少年期にはもうひとつ、彼の人格を形成したと考えられている大きな要素があります。
それは父・倉五郎と母・関の夫婦関係。
母の関は谷崎家の先代当主の娘であり、父の倉五郎は婿養子にあたりました。
これは先代が娘を溺愛し、自身が築いた財産を継承しようとしたがためのこと。
長男は奉公に出され、家業を継いでいないんですよね。
こんな感じで箱入り娘として育った関は気が強く、夫を尻に敷くタイプの妻だったといいます。
家業が傾いて貧乏暮らしを強いられてからも、朝早くに起きて炊事をするのは倉五郎の役目。
関は
「あんたのせいでこんな生活しなきゃならないのよ」
と、いわんばかりの振る舞いだったのだとか。
潤一郎の作品は、女性崇拝の思想が多岐に渡って反映されているのも大きな特徴です。
その基礎を築いたのが、少年期の女性優勢の家庭環境だといわれています。
ちなみに関さんは、当時『美人絵双紙番付』というランキングで大関に選ばれるぐらいの美人。
そりゃあおじいちゃんも猫かわいがりするわけだ…。
文壇デビュー
東京帝国大学へ進んだ潤一郎は、1910年から同校内で小山内薫、和辻哲郎らと第二次『新思潮』を刊行。
『刺青』や『麒麟』といった、のちに話題となる作品を発表していきます。
一方、大学は学費未納で退学処分に。
文壇デビューを目指し、完全に執筆業に傾倒していった感じですね。
時代柄評価されなかった作風

ただ潤一郎の思惑とは裏腹に、彼の作風は当時、誰にも見向きされないような状況にあったのだとか。
潤一郎自身、19~25歳ごろまではいくら作品を発表しても評価されず、
「ほんとに文学で食っていけるのか…?」
と不安に苛まれる日々だったと語っています。
というのも、当時の主流は島崎藤村を始めとする自然主義文学。
筆者の境遇をありのままに描いたような現実的な作品がよしとされていたためでした。
潤一郎の作品といえば、
・マゾヒズム
・女性崇拝
と、日本人の日常からは明らかに逸したものです。
たとえば、このときの代表作『刺青』は、江戸時代の刺青師が女性に刺青を掘る過程で、その女性を魔性の女に仕立て上げるという内容。
大衆からしてみれば
「江戸時代?刺青師?魔性の女に仕立て上げる…?」
という感じ。
見慣れない世界観から、新しすぎてよくわからない小説だと映ってしまったわけです。
永井荷風の絶賛で文壇の寵児に

そんな時節を見て、潤一郎が頼りにしたのが、作家・永井荷風です。
荷風は実業家である父の意向でアメリカやフランスに渡り、現地で銀行員を務めた経験のある人物。
その日々をもとにしたエッセイなどで注目を集めていた作家でした。
日本の大衆に受け入れられない作風も、欧米の感覚をもつ荷風になら理解してもらえるはず。
そう踏んだ潤一郎は荷風を訪ね、
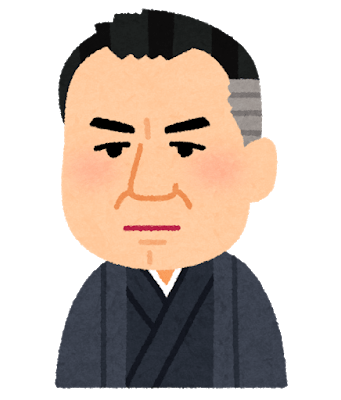
と、原稿を手渡すのです。
すると取り上げているテーマの新しさや文章の完成度などに感心した荷風は、潤一郎の作品を文芸誌『三田文学』にて絶賛。
潤一郎は一躍、文壇での地位を確立するにいたるのです。
文学だけでなく、いかに作品を世に流出させていくか、潤一郎はそういった戦略的な部分でも長けていたのですね!
3度の結婚
潤一郎は生涯を通し、実に3回の結婚をしています。
バツ2ぐらいなら珍しい話でもないし、むしろそれもこの時代の作家らしい…
なんて、思う人もいるでしょう。
しかし潤一郎の結婚を見出しにして取り上げることには、それにも増した理由があります。
この3人の妻との関係を通して、彼の作品にも通じる異様な価値観がこれでもかと示されているのです。
一人目の妻・千代の場合
まず、最初の妻・石川千代と結婚したのが1915年、29歳のころの話。
『刺青』などが注目され、作家として旬を迎えようという、そんな時期のことですね。
潤一郎が好きだったのは千代のお姉さん

実は潤一郎が千代と結婚したのは、彼女のことを好きだったからではありません。
潤一郎が好きだったのは千代の姉で、芸者の初でした。
気が強く、男勝りなところがある初は潤一郎にとってまさにドストライクの女性。
潤一郎はこの初にプロポーズをするのですが、これを受けた初はなんと
「だったら、代わりに妹の千代をもらってあげて!」
と、千代を紹介するのです。
この経緯から潤一郎は千代と結婚することになるのですが…
なんと彼女の性格が初とは真逆。
旦那の一歩後ろを歩くような穏やかなタイプの女性で、刺激的な関係を求める潤一郎にとっては物足りなかったようなのです…。
佐藤春夫に妻を譲る?小田原事件
あるとき、事情あって潤一郎の一家は、千代の妹・せい子を引き取ることになります。
初とは似ても似つかない千代に対し、このせい子は初によく似た強気でわがままな側面をもつ少女でした。
そう、こともあろうに潤一郎は、妻そっちのけでせい子に入れ込むようになるのです。
この様子を見て、千代を不憫に思ったのが、潤一郎と懇意にしていた作家・佐藤春夫でした。
せい子に夢中で留守がちな潤一郎に代わり、千代や長女の鮎子と一家団欒の席を共にするようになった佐藤。
ある日、偶然その光景を目にした潤一郎はなんと
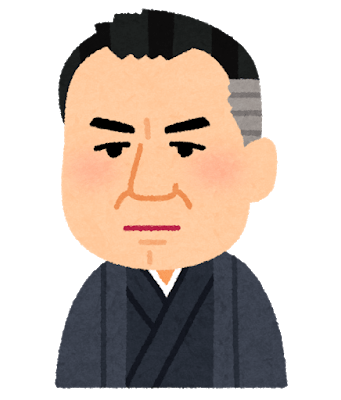
と、佐藤と千代に交渉するのです。
普通の旦那なら
「人の嫁に手え出そうってのか!」
と、激怒しそうなもの。
せい子に夢中だった潤一郎からすれば、千代を好きになってくれる男性が現れたことは都合のいい話だったのです。
そして佐藤と千代に話をつけたあと、潤一郎はせい子に結婚を迫るわけですが…
このときせい子は15歳、潤一郎は35歳という歳の差。
やはりというかなんというか…
「は?おじさんと結婚なんてするわけないじゃない」
と、フラれてしまいます。
すると潤一郎は、すっかりその気になっていた佐藤と千代に
「やっぱ結婚の話はなしで!」
と、待ったをかけることに。
「もう意味がわからん!」
と、怒った佐藤と絶交するに至ったというのが、当時文壇を騒然とさせた「小田原事件」の全貌です。
たしかに佐藤が起こるのもわかるぐらい、めちゃくちゃな話ですよね…。
結果的にハッピーエンド?細君譲渡事件
…と、一時は絶交にまでいたった佐藤春夫と潤一郎でしたが、1930年ごろにはすっかり和解。
この年に潤一郎は千代と離婚し、なんと、ほんとに佐藤に譲ってしまうこととなります。
3人の連名で声明も発表され、今度は「細君譲渡事件」として、文壇を騒がせるのでした。
こんな感じで千代とは円満に離婚がなされ、以後は娘の鮎子を含め、佐藤ともども交流が続いていったとのこと。
結果的にハッピーエンドなのか…?
ともかく、紆余曲折あっても潤一郎を慕う佐藤や千代の器の大きいこと。
ちなみにこのとき潤一郎が好きだったせい子との関係をモデルに書かれたのが、1924年発表の『痴人の愛』です。
日本人離れした可憐な少女を引き取ることになった主人公が、彼女を理想の女性に育て上げるも、傲慢に育った彼女にいいように扱われてしまう。
うん、あらすじだけを見てみてもやっぱり危なっかしいですね。
二人目の妻・丁未子の場合
20歳年下のせい子にはフラれてしまった潤一郎。
しかし千代と離婚した翌年、1931年には、21歳年下の女学生、古川丁未子と結婚することになります。
いったいどうやってそんな若妻とお近づきに?
潤一郎の大ファンだった丁未子
丁未子はもともと、大阪女子専門学校の生徒でした。
当時潤一郎が執筆していた『卍』の舞台が大阪ということで、大阪弁を導入したいという流れから同校の生徒を頼り、縁ができたとのこと。
なんでも、依頼を受けたのは別の人だったものの、丁未子が潤一郎の大ファンで、
「どうしても会いたい」
と、連れ立ってやってきたのが最初だったようですね。
つまり潤一郎との結婚は丁未子にとっては願ってもない話で、だからこそ親子ほどの歳の差婚も実現したといえます。
しかし…そんな若妻との結婚生活は、2年で終わりを迎えることとなってしまうのです。
根津松子との不倫

丁未子との結婚生活がうまくいかなくなったのは、結婚する少し前から潤一郎が密かに想いを寄せていた女性、根津松子の存在によってでした。
松子と潤一郎が知り合ったのは、作家・芥川龍之介を介してのことです。
芥川と潤一郎は仲が良く、このときは旅館で飲み食いしながらあれやこれやと話していたとのこと。
これ以前にふたりは文芸誌『改造』にて「小説に筋が必要か否か」という論争を繰り広げ、巷では話題となっていました。
この関係性を見るにそれも揉めていたわけではなく、単に議論していたにすぎないことがわかりますね。
そしてこのときこの旅館に駆け付けたのが、芥川ファンの松子。
当然、松子の目当ては芥川なのですが、その場に居合わせた潤一郎のほうが松子を好きになってしまうわけです。
しかし松子は大阪の豪商の人妻として恵まれた暮らしをしており、潤一郎も入る隙がないと、一時は身を引くことに。
そこから丁未子との結婚に至るわけですが、あるとき、松子から夫の商売や夫婦関係がうまくいっていないと相談を受けます。
そして潤一郎は次第に松子と不倫関係に…。
このとき潤一郎は借金が原因で住むところを追われており、松子は根津家の隣の別荘を貸し出したりもしていました。
丁未子は家事が苦手だったため、松子が料理をしにたびたび出入りしていたという話も。
それでも、若い丁未子は30代の松子に負けることなどないと、潤一郎と懇意にすることを容認していたようですね。
三人目の妻・松子の場合
上述のような経緯から、1934年、潤一郎は丁未子と離婚。
そして翌年、同じく旦那との離婚が成立した松子と再婚することとなります。
以降、彼女は終生の妻として潤一郎に寄り添うことに。
そしてこの松子こそ、やはり潤一郎の理想の女性像そのものだったようです。
妻に尽くすマゾヒズム
1933年に発表された『春琴抄』の春琴という女性は松子がモデルです。
春琴は盲目の三味線奏者で、春琴抄は彼女の虜となる従者との関係が描かれた作品となっています。
松子は潤一郎の意図を器用に汲める女性で、執筆中は春琴になりきり、潤一郎を従者のごとく扱ったという話。
と、これはあくまで作品のインスピレーションを湧かせるため、かと思いきや、実は潤一郎は普段から、松子に対してまるで従者のように振る舞っていたのだとか…。
潤一郎は松子に宛て、実に300通に上る手紙を送っており、そのなかには自身を下僕とし
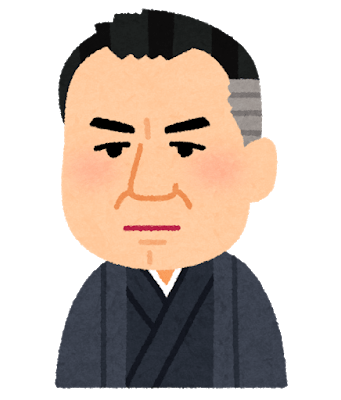
なんていう一文もあります。
これが世にいう谷崎潤一郎の女性崇拝…要するにドMです。
松子の姉妹をモデルにした『細雪』

潤一郎の作品で一番、一世を風靡したといえるのが、松子の生家である森田家の四姉妹を主人公にした『細雪』です。
松子の父・森田安松は大阪にて造船所を営む大富豪。
『細雪』には、その娘として育った四姉妹の暮らしぶりが、まるでノンフィクションのごとく反映されています。
ただ…この作品は第二次世界大戦下にあった日本では時局にそぐわないと、発禁処分が下されることに。
上流階級の暮らしを想起させる内容が、贅沢を悪とする戦時中には不適切だと見られてしまったのですね。
しかし潤一郎は、日の目を見ないそんななかでも『細雪』を完結まで書き続けました。
そして戦後、情勢が変わった日本でこの作品が受け入れられると
・朝日文化賞
・文化勲章
など、名立たる賞を次々に受賞することに。
苦境に立たされても執筆をやめなかった潤一郎には、必ず受け入れられる時代が来るという確信があったのでしょうね。
この『細雪』は『蓼喰う蟲』などとともに海外版に翻訳もされ、潤一郎が1958~64年にかけ、計7回のノーベル文学賞候補に挙げられる理由となった作品でもあります。
入門としておすすめの一作でもありますね。
『源氏物語』の現代語訳は家族を養うため。しかしこだわりようはハンパない
潤一郎が『源氏物語』の現代語訳を始めたのも、松子との結婚がきっかけでした。
新しい家族を養うため、中央公論社に月々の報酬を取り付けたうえで、この作品に取り組み始めたのです。
思いっきり食い扶持を稼ぐためだけの仕事に見えますが…かといって潤一郎に妥協の二文字はありません。
このとき暮らしていた神戸の邸宅は、平安朝の寝殿造りという様式で建てられた建物。
源氏物語の世界観に浸るため、なんと私生活まで平安時代にタイムスリップした風を装っていたのです!
潤一郎はこのように作品のインスピレーションを湧かせるため、住まいにはとことんこだわっており、生涯に42回も転居を繰り返しました。
3回結婚しているせいもありますが、それにしても異常なほど多い…。
作品の完成度にこだわるその姿勢には恐れ入るものがありますね。
晩年まで続いた執筆活動・女性崇拝は息子の嫁にも…

晩年になると、潤一郎は持病の高血圧症を悪化させ、右手の麻痺を患います。
こうなると小説を自分で執筆することは困難。
以降は秘書を頼った口述筆記にて、作品を描いていくこととなります。
そんな状態になってまで執筆を続けようとしたことがまずすごい!
潤一郎ほど、長期間に渡って休まず作品を出し続けた作家はいないといわれるほど、彼は終始精力的に執筆を続けた人でした。
で、このころになっても、潤一郎の女性崇拝の思想は健在。
次にそのターゲットとなったのは、松子の連れ子・清治の嫁・千萬子です。
潤一郎が京都で暮らしていたころ、清治夫妻は谷崎家の離れにて暮らしていました。
そのため千萬子と潤一郎も接する機会が多く、潤一郎は彼女のことを相当に気に入るのです。
千萬子は画家・橋本関雪の孫にあたる人物で、その誇りからか、売れっ子の潤一郎にも気後れしなかったとのこと。
潤一郎はそういう強気な女性が大好きですから、崇拝の対象にもなったわけですね。
千萬子は松子と同じく、潤一郎から多くの手紙を受け取っており、そのなかには
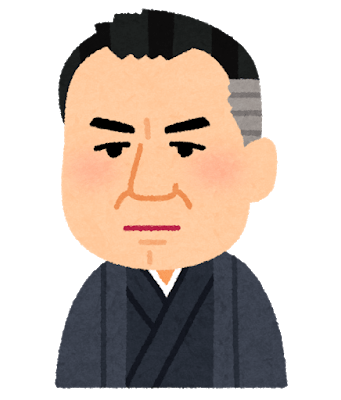
などという一文もありました。
70を超えたおじいちゃんからこんなアプローチされたら、正直怖い…。
このころに書かれた『瘋癲老人日記』は、そんな千萬子とのやりとりをモデルにした作品。
老人の性欲を描くという、これまた斬新な内容となっています。
きょうのまとめ
谷崎潤一郎は生来の天才であったことに加え、自らの人生経験をありのまま反映していくことで無二の作品群を残しました。
特に目を引くのは、やはり波乱の連続だった女性関係。
ときには修羅場さえも作品にしてしまう潤一郎は、まさに生涯を小説に捧げた文豪といえます。
ある種めちゃくちゃだけど、ある種かっこいい…なんだか複雑な感情を抱かせる人物でした。
最後に今回のまとめです。
① 少年時代は神童と呼ばれた谷崎潤一郎。家業が傾き学費の支払いが困難になると、才能を惜しんだ教師たちが進学を支えた。中学時代は2年から3年に飛び級。
② 潤一郎は生涯に3回の結婚を経験した。押しの強い女性との刺激的な関係を求めることが、離婚のほとんどの原因。女性崇拝の思想は作品にも強く反映されている。
③ 手が動かなくなっても執筆を続けた。類を見ないほど長期に渡る精力的な活動から、文化勲章、ノーベル賞候補などにも選ばれる。女性崇拝の思想も生涯健在。
ともあれ、潤一郎の作品に対するこだわりには見習いたいと思わされる部分が多々あります。
住まいや私生活の振る舞いまでを作品に準じていったその姿勢。
ここまでできれば、世界に認められるのも道理な気がしますね。
その他の人物はこちら
明治時代に活躍した歴史上の人物
関連記事 >>>> 「【明治時代】に活躍したその他の歴史上の人物はこちらをどうぞ。」
時代別 歴史上の人物
関連記事 >>>> 「【時代別】歴史上の人物はこちらをどうぞ。」