昭和初期の時代、太宰治などに代表される無頼派の一員として、個性的な作品を世に送り出し注目を浴びた作家
織田作之助。
大阪生まれ大阪育ちの彼の作品には大阪庶民の風合いが反映され、登場人物がとにかくユニーク。
ただ発想が自由過ぎて、しばしば世間の風潮と折り合いがつかず、発禁処分を受けるようなこともありました…。
いかにも破天荒な作之助の生涯を辿ると、33年という非常に短い一生を遂げていることにまた驚かされます。
織田作之助とはいったいどんな人物だったのか、いかにして唯一無二のその作風は生み出されていったのか。
今回はその生涯に迫ってみましょう。
タップでお好きな項目へ:目次
織田作之助はどんな人?

織田作之助
出典:Wikipedia
- 出身地:大阪府大阪市南区(現・天王寺区)
- 生年月日:1913年10月26日
- 死亡年月日:1947年1月10日(享年33歳)
- 昭和初期の時代において、太宰治、坂口安吾らに並ぶ無頼派と呼ばれた作家。短編小説を得意とし、大阪庶民の風合いを感じさせる人間味ある登場人物が魅力。
織田作之助 年表
西暦(年齢)
1913年(1歳)大阪市南区(現・天王寺区)仕出し屋「魚春」を営む織田鶴吉、たかゑの長男として生まれる。
1934年(21歳)第三高等学校(京都大学教養部の前身)の卒業試験中に喀血し、療養生活を余儀なくされる。
1935(22歳)作家活動を開始。青山光二らと同人誌『海風』を創刊する。
1936年(23歳)第三高等学校へ復学するも勉強への意欲を失い、出席不足で退学。
1938年(25歳)処女作『雨』を発表。
1939年(26歳)同棲していた宮田一枝と結婚。新聞社への勤務を経験する。『俗臭』が芥川賞候補、『夫婦善哉』が改造社の第一回文芸推薦作品となり、作家として注目されるようになる。
1944年(31歳)妻・一枝ががんで亡くなる。
1946年(34歳)ふたり目の妻・笹田和子と再婚。
1947年(34歳)結核を患い喀血し、東京病院に入院。1月10日、この世を去る。
織田作之助の生涯
1913年のこと、織田作之助は仕出し屋「魚春」の長男として、大阪市南区(天王寺区)に生まれます。
作之助が生まれた当時、両親は駆け落ち中の身で正式に籍を入れていなかったため、誕生時は母の兄・鈴木安太郎の甥という形を取り、鈴木姓をつけられていました。
その後、13歳のころに両親が入籍したため、父方の織田姓を名乗るようになります。
いきなり訳ありの家庭から始まる生い立ちも、作之助のその後の波乱を予期しているかのようですね。
小学校始まって以来の天才少年

作之助は仕出し屋の長男ということで、いわゆる庶民の子です。
決してエリートとはいえない家柄ですが、学生時代は成績優秀で、周囲からは天才扱いを受けていました。
18歳のころには京都大学教養部の前身にあたる第三高等学校への入学を決め、これは母校の東平野尋常高等小学校の出身者では初の快挙。
「入学式に小学校の生徒総出で見送らせてほしい」
と申し出があったという逸話もあるほどです。
庶民の出だったゆえ、当時としては余計に取り沙汰されたのでしょうね。
親族としても誇らしいことだったようで、作之助の姉・タツの夫・竹中国治郎にしてもこの三高の学費を全額援助するなど、大層に世話を焼いています。
そんな感じで周囲から全幅の期待をかけられていた作之助ですが、1934年の卒業試験で体調を崩し、喀血したことで大きくその人生が狂っていきます。
作家としての大成

病気の影響で卒業試験を合格できず、休学を余儀なくされた作之助。
彼はこの期間で文学に目覚め、作家を志すようになっていきます。
その後、大学に復学したころには学習意欲がすっかりなくなっており退学。
皮肉なもので、小学校始まって以来の天才少年は病気をきっかけに学業を諦め、作家の道をひた走っていくことになるのです。
大学を辞めてからは新聞記者で生計を立てていた時期もありましたが、26歳のころに同人誌『海風』に掲載した『俗臭』が芥川賞候補、さらに代表作の『夫婦善哉』が改造社の第一回文芸推薦作品となったことで一躍有名になります。
作之助はこれを機に上京し、執筆活動に専念していくのです。
庶民の人間臭さが反映された織田作之助の作品群
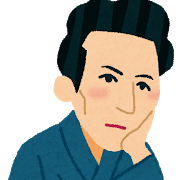
作之助の作風は太宰治や坂口安吾、石川淳らと名を連ねる無頼派と呼ばれ、ファンからは「オダサク」の愛称で親しまれていました。
作品の登場人物は往々にして一癖あり、どこか庶民を感じさせる人間臭さにあふれているのが特徴。
代表作の『夫婦善哉』を例に挙げてみると、常に金銭問題に悩まされる夫婦の滑稽なやり取りが魅力の作品となっています。
このほかにも『天衣無縫』など、夫婦を題材にした話がちらほらあるのはどこか大阪庶民らしいですね。
なお自身をモデルにした自伝的小説『青春の逆説』は当時、戦時中の時節にふさわしくないとして、発禁処分を受けています。
この作品の主人公・毛利豹一がまた相当な変人で、戦時中の重苦しい空気など意にも止めず、面白おかしい作品を書き続けていたところが作之助らしいです。
妻の死と覚せい剤の常用

晩年になるに連れ、作之助の生活はどんどん壮絶を極めていきます。
三高時代に知り合った宮田一枝と結婚した作之助は、大の愛妻家としても知られていました。
しかしその妻は作之助が31歳のころ、がんで亡くなってしまうのです。
以来、作之助は一枝の遺髪と写真を生涯肌身離さず持ち歩いていたのだとか…。
そしてこのころ、作之助が常備していたものは、一枝の遺品のほかにもうひとつありました。
戦後、日本市場で急速に出回り出した覚せい剤・ヒロポンを打つための注射器です。
当時は覚せい剤の危険性が認知されておらず、禁止する法律もなければ、普通に薬局でも売っているような時代だったんですよね…。
で、晩年の作之助ときたら、そりゃあもう馬車馬のごとく働いており、ヒロポンを打っていたのも徹夜仕事を乗り切るためでした。
もともと病気がちな身体にムチを打ち、相当な無理を強いながら執筆活動に勤しんでいたのです。
妻・一枝に先立たれ、自暴自棄になっていた…?
とも取れますが、これはなにも特別なことではなく、作之助は生来向こう見ずな性格で、多少の無理はいとわない人だったといいます。
しかしそんな無理がたたってか、1946年の年末に作之助は結核を患って入院。
そのまま翌年の1月10日、33歳の若さで帰らぬ人となります。
きょうのまとめ
織田作之助の走馬灯のように過ぎ去った生涯は、彼が得意とした短編小説さながら。
山あり谷ありの波乱に満ちたものでした。
その波乱の連続こそが、彼の興味深い作品の源だったのでしょうね。
最後に今回のまとめをしておきましょう。
① 織田作之助は小学校始まって以来の天才。学業優秀で、第三高等学校の入学時は出身小学校から「生徒総出で見送らせてほしい」と要請がくるほどだった。
② 病気で大学を休学になった期間に作家活動に目覚める。作品が芥川賞候補や改造社の文芸推薦作品に選ばれたことで、その地位を確立していった。
③ 晩年は亡き妻の遺髪と写真、ヒロポンを打つための注射器を常備していた。昼夜問わず馬車馬のごとく働いたことが寿命を縮めたとも…。
晩年までの経緯を振り返ってみると、織田作之助という人物はこう、一瞬に濃縮して才能を発揮した人だったのだな、などと考えさせられます。
もう少し長く生きていたらさらに多くの作品が生まれていた…というのはよくいわれることですが、作之助の作品は一瞬に濃縮した才能があってこそ、生まれるものだったのかもしれませんね。


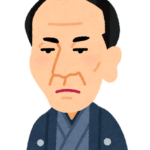





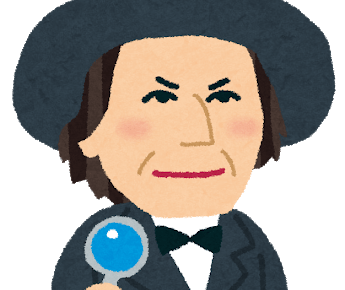
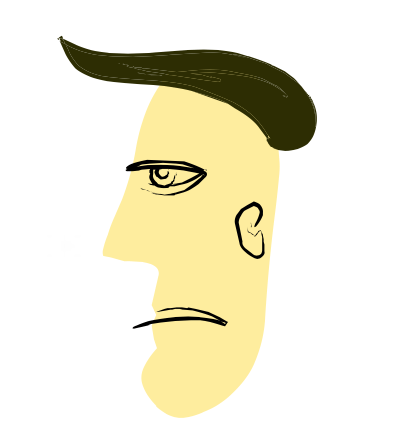
コメントを残す